「人的資本経営」という言葉を耳にする機会が増えました。しかしながら、これはまだまだ大企業が取り組むべきことと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、「人的資本経営」は、決して大企業だけのものではありません。むしろ、限られた資源(リソース)の中で最大限の成果を出さなければならない中小企業こそ実践すべきものだと、私は考えています。
そこで、本記事では、中小企業の経営者や管理部門の責任者に向けて、「人的資本経営」の基本の考え方から、なぜ今、中小企業にとってそれが重要なのか、そしてすぐに実践することができる具体的な取組みまでを解説していきたいと思います。
執筆者プロフィール
 人材マネジメントコンサルタント 笹谷 浩二(ささや こうじ)
人材マネジメントコンサルタント 笹谷 浩二(ささや こうじ)
1995年、横浜市立大学商学部卒業後、松下電器産業㈱(現: Panasonic)に入社し、人事部門に配属。
以降、日系・外資系企業の人事社員・マネージャーとして20年以上従事する中で、人事戦略の企画・立案、制度設計からその運営・運用までを経験。
2018年人事コンサルティング会社(シナジー&エフェクト合同会社)を設立して独立。
企業人事としての知識・経験も活かし、クライアント企業(数千名〜数名規模の会社まで)に対して、主に以下のご支援を実施中
① 人事戦略・人事制度構築支援、
② 研修・トレーニング、コーチング、
③ 労務問題対応支援等、人的資本経営実現・実践
・ISO30414リードコンサルタント/アセッサー *ISO30414:人的資本に関する情報開示ガイドライン
・GCS認定コーチ
第1章:人的資本経営とは何か? 3つの要素からひも解く
「人的資本経営」とは何か? 経済産業省のHPには、次の定義が掲載されています。
「人的資本経営とは、人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方のこと」
人材の「コスト」の側面に、大きなウエイトを置いて見ている経営者の方であれば、この定義を見て「そうか、こういう考え方・観点が重要なのか!」と衝撃を受けるのかも知れません。
しかし私の認識ですと、そうした例は極めて少数であり、多くの経営者の方は、この定義を見て、「なんだ、これまで私が行なって来た、『人を大切にする経営』そのものではないか。それと何が違うのか?」という疑問・問いを抱くのではないでしょうか?
この問いに答えるとすれば、「『人的資本経営』とは、『人を大切にする経営』の精神を大切にしつつ、いくつかの要素を加えてアップデートしたもの」と言うことができると考えており、つまり、この「いくつかの要素」が「人的資本経営」と「人を大切にする経営」の違いになると考えます。
では、その要素とは何でしょうか?
ここでは3点挙げたいと思います。
1.人を資本として捉える
「人的資本」、つまり、「人を資本として捉える」とはどう言うことなのでしょうか?
「資本」とは「価値を生み出す源泉となる要素」のことであり、その生み出される価値は、「投資」によって大きくなってきます。
つまり、「人的資本経営」とは、人(人の集合である組織も含め)を資本と捉えて「投資」を行うことで、人が生み出す価値を大きくし、ひいては「企業価値を向上」させると言うことになります。
2.データ分析や合理的判断などに基づいた投資
ところで、皆さんの中で株式投資等をされる方は、その「投資」を成功させるために、どのようなことをされるでしょうか?
多くの人は、何に対して、いくら投資するかを決定するために、まず、投資先の候補に関する現状を出来るだけ正確に把握し、リスクやリターンの程度を分析して、合理的に投資対象や程度を検討・判断しようとするのではないでしょうか?
人への投資も同じと言えます。従来から「人」に関することについては多くの場合、勘や感覚に頼っていた・頼っていると言う経営者の方が少なくないと思います。
もちろん勘や感覚も大事ですが、「人的資本経営」における人材への投資(様々な施策)についても、それを裏付けるデータ・指標に基づく分析や、合理的な検討・判断を行った上で実行していくことが重要です。
それらを踏まえて、2点目の要素をまとめますと、「データや指標に基づく分析、合理的な検討・判断に基づく人材への投資を行う」となります。
3.情報の開示
最後に3点目は、「人的資本に関する情報を開示する」という点です。
「人的資本経営」を進めていくに当たって重要となる、「人的資本に関する情報開示のガイドライン(ISO30414)」が、2018年12月に国際標準化機構(ISO)から発表されています。
具体的には、11項目58指標 で構成されたガイドラインで、大企業だけでなく、中小企業にも開示が推奨される指標が含まれています。
では、なぜ、何のために、こうした指標の開示が推奨されているのでしょうか?
現代のように変化が激しく、複雑、不確実な環境の中で、企業が将来に向けて成長していけるかどうかは、その企業に集う人材にかかっています。
にもかかわらず、これまでは、企業が人材にどれだけ投資を行い、その強化にしっかり取り組んでいるのか、ということについて、投資家を含む多様なステークホルダーなど、客観的な立場から見ることは難しかったと言えます。
端的な表現になりますが、それらを「見える化」しましょう、と言うことになったのが、情報開示の理由です。
とは言え、この人的資本に関する情報の開示はあくまで推奨であり、義務ではありません。よって、中小企業の経営者の皆さんの多くにとっては、まだまだ身近ではない話に聞こえることと思います。
しかしながら、既に、投資家はもちろんのこと、お客様、融資元である銀行や保険会社、はたまた昨今の深刻な人員・人材不足の状況において、潜在的な採用応募者の方々も、人的資本に関する情報に、経営者の皆さんが思う以上に注目するようになってきています。
そして今後は、それぞれのステークホルダーが、投資、ビジネス、融資や応募・入社等の判断材料にしていくことになると言うことを理解する必要があるのです。
第1章まとめ
以上第1章では、「人的資本経営」とはなにか、を紐解くために、「人的資本経営」と「人を大切にする経営」の違いから、「人的資本経営」の3つの重要な要素について触れて来ました。
それらを踏まえて、次の章では、「なぜ今、中小企業にとってこそ『人的資本経営』が重要なのか?」について触れていきたいと思います。
第2章:なぜ今、中小企業にとってこそ人的資本経営が重要なのか?
第1章を読まれて、それでもやはり「人的資本経営」は大企業が取り組むべきことと思われている方も相当数いらっしゃるのではないかと思います。
しかしながら、私は、以下3つの理由から、やはり、中小企業にとってこそ、「人的資本経営」が重要であり、また取り組み易くもあると考えています。
1.一人一人が事業に与えるインパクトが大きい
中小企業は、大企業に比べて、資金・人員ともに制約があることから、人材一人一人が事業に与えるインパクトが大きいと言う点が挙げられます。
中小企業は、大企業のような莫大な資金力やブランド力で勝負することは難しいのが現実です。しかしながら、「人」という資本においては、大企業にも負けない強みを持つことが可能であると考えます。
また、社員一人ひとりの顔が見える規模と言う中小企業の特徴は、投資としての、きめ細やかな取組みが実施し易いと言うメリットがあります。
そして、社員が自社のビジネスに深く関わり、成長を実感できる環境や機会を提供し易いなど、これらの利点を活かした経営は、大企業には真似のできない中小企業ならではの強みになると考えます。
2.人員・人材不足への対応となりうる
「人的資本経営」の取組みが、深刻化する人員・人材不足への対応策になる点が挙げられます。
少子高齢化に伴う労働人口の減少は今後も加速していくと予測されています。特に中小企業は、大企業と比べてブランド力や待遇面で劣ることが多く、優秀な人材の確保に苦戦するケースがほとんどかと思います。
そのような状況にあって、「人的資本経営」に取り組むことは、「この会社で働きたい」と思える魅力を高めることにつながると考えられます。
これにより、貴重な人材の流出を防ぎ、定着率を高める効果が期待できるとともに、採用活動においても、「人=社員の成長を支援する企業」「働きやすい環境整備を継続的に行っている企業」として、強力なアピールポイントになり得ると考えます。
さらに言えば、近い将来、「人的資本経営」の取組みは、賃金と同レベルで、あって当たり前、実施されていて当たり前のものとなる可能性が高いと考えられることから、その意味で、今から取り組んでおく必要があるとも言えると考えます。
3.経営改革の足掛かりに
「人的資本経営」に取り組むことを通じて、経営改革を進めることができます。
現在、中小企業を取り巻く環境は、ますます厳しさを増しており、その要素は、先に挙げた人員・人材不足に加え、物価高、賃金の高騰、関税問題、グローバル競争の激化等、挙げれば切りがありません。
そうした状況の中で、「人的資本経営」は、企業の生産性向上はもちろん、財務的な結果や、持続的な事業成長を可能とする取組みになるのです。
第2章まとめ
以上第2章では、なぜ今、中小企業にとってこそ人的資本経営が重要なのか?について述べて来ました。
続いて第3章では、中小企業が「人的資本経営」の取組みとして、どのようなことを行ったら良いのか?その「第一歩」の取組みについて触れたいと思います。
第3章:中小企業が取り組むべき「最初の一歩」
ここまで述べてきたように、「人的資本経営」は中小企業にこそ必要な取組みであると考えますが、実際に取り組もうとすると、「何から始めれば良いか分からない。」「難しい分析やシステム導入が必要なのではないか。」といった不安や、疑問を感じる方も少なくないでしょう。
結論から申し上げれば、「最初の一歩」は「現状を正しく把握し、優先度の高い領域に小さく着手すること」であると考えます。いきなり、ISO30414の全指標を網羅する必要はないのです。
では、具体的にどのような取組みをすれば良いでしょうか。以下の3つのステップで進めることをお勧めしたいと思います。
ステップ1:自社の人的資本の現状を「見える化」する
まず取り組むべきは、現状把握です。「人的資本経営」の出発点は、勘や感覚だけでなく、データに基づいた現状の理解にあります。
中小企業であれば、以下のような基本的な指標の把握から始めると良いでしょう。
• 社員数、平均年齢、勤続年数
• 新卒・中途の採用人数、採用コスト、離職率
• 総額人件費
• 売上高生産性、労働分配率
• 有給取得率、残業時間
• 教育研修にかけている時間・費用 等
これらの情報を把握するだけでも、自社の「強み」と「問題」が明確に見え始めます。
ステップ2:問題に応じた「小さな投資」から始める
次に行うのは、把握した問題解決に繋がる小さな人的資本への投資の実施です。
例えば
• 若手社員の離職率が高い
→ メンター制度やキャリア面談の導入や、上司の人材マネジメント力強化のための研修を実施する
• 採用がうまくいかない
→ 自社の魅力を整理するとともに、採用媒体や採用チャンネルを見直す
→ 評価制度等の社内制度や、施設・設備等の社内インフラをできるところから、できる範囲で改善する
• 生産性が伸び悩んでいる
→ OJTを基本とする業務改善や、Off-JTによるスキルアップ研修を実施する 等
中小企業にとって重要なのは、大きなコストをかけずに即効性のある施策を積み重ねることです。
これらの実践により、生産性の向上や、社員のエンゲージメントや定着率の改善が見込めます。
ステップ3:成果を社内外に共有・開示し、次の投資へつなげる
最後に、取り組みの成果を会社のIRレポートやHP等で、社内外に共有・開示することが挙げられます。
取組みによる成果を共有・開示することで、社内においては、社員の安心感やモチベーション向上につながります。
さらに、社外にも共有・開示することで、お客様、株主、金融機関や採用候補者等も含む、多くのステークホルダーに、貴社が「人材に積極的に投資する企業」として認知され、信頼を得ることに繋がります。
以上のステップ1〜3を繰り返し実践して習慣化することにより、「人的資本経営」は単なる理論ではなく、中小企業の成長を支える実践的な経営手法・組織文化になるのです。
おわりに
本記事では、「中小企業の経営を強化する「人的資本経営」取り組むべき「最初の一歩 」をテーマに述べて参りました。大事なのは「小さな一歩」を踏み出すことです。まずは前述のステップ1から始めてみましょう。それが次第に広がり、習慣化されることで、その小さな一歩は、数年後には以下のような変化に繋がっていくことでしょう。
• 人材の定着と採用力の向上
「ここで働き続けたい」「この会社で成長できる」という社員が増え、採用市場での魅力も高まる。
• 生産性の向上と業績への波及
社員の能力発揮が進み、現場改善や業務効率化が進むことで、売上や利益にも直結する。
• 組織文化(カルチャー)の進化
データに基づく合理的な投資と、社員の成長実感が組み合わさり、挑戦的で持続的な組織文化(カルチャー)が形成される。
繰り返しになりますが、「人的資本経営」は、決して大企業だけのものではありません。中小企業だからこそ、早く、小さく始め、着実に積み上げることで、事業の持続的成長と社員の幸せを同時に実現することに繋がるのです。
本記事が、貴社が「人的資本経営」の「最初の一歩」を踏み出すきっかけになれば幸いです。
またもし、取り組みに不安や疑問がある場合は、いつでもご相談いただければと思います。
▼ISO30414の11項目58指標
| 11項目 | 58指標 | |
|
1 |
倫理とコンプライアンス |
(1)提起された苦情の種類と件数/(2)懲戒処分の種類と件数/(3)倫理・コンプライアンス研修を受けた従業員の割合/(4)第三者に解決を委ねられた紛争/(5)外部監査で指摘された事項の数と種類 |
| 2 |
コスト |
(1)総労働力コスト/(2)外部労働力コスト/(3)総給与に対する特定職の報酬割合/(4)総雇用コスト/(5)1人当たり採用コスト/(6)採用コスト/(7)離職に伴うコスト |
| 3 |
ダイバーシティ |
(1)年齢/(2)性別/(3)障害/(4)その他/(5)経営陣のダイバーシティ |
| 4 |
リーダーシップ |
(1)リーダーシップに対する信頼/(2)管理職1人当たりの部下数/(3)リーダーシップ開発 |
| 5 |
組織風土 |
(1)エンゲージメント・満足度・コミットメント/(2)従業員の定着率 |
| 6 |
健康・安全・幸福 |
(1)労災によりい失われた時間/(2)労災の件数(発生率)/(3)労災による死亡者数(死亡率)/(4)健康・安全研修の受講割合 |
| 7 |
生産性 |
(1)従業員1人当たりEBIT・売上・利益 |
| 8 |
採用・異動・離職 |
(1)募集ポスト当たりの書類選考通過者/(2)採用社員の質/(3)採用にかかる平均日数/(4)重要ポストが埋まる迄の時間/(5)将来必要となる人材の能力/(6)内部登用率/(7)重要ポストの内部登用率/(8)重要ポストの割合/(9)全空席中の重要ポスト空席率/(10)内部異動数/(11)幹部候補の準備度/(12)離職率/(13) 自発的離職率/(14)痛手となる自発的離職率/(15)離職の理由 |
| 9 |
スキルと能力 |
(1)人材開発・研修の総費用/(2)研修への参加率/(3)従業員1人当たりの研修受講時間/(4)カテゴリー別の研修受講率/(5)従業員のコンピテンシーレート |
| 10 |
後継者計画 |
(1)内部継承率/(2)後継者候補準備率/(3)後継者継承準備度(即時)/(4)後継者継承準備度(1-3年、4-5年) |
|
労働力 |
(1)総従業員数/(2)総従業員数(フルタイム・パートタイム)/(3)フルタイム当量(FTE)/(4)臨時の労働力(独立事業主)/(5)臨時の労働力(派遣労働者)/(6)欠勤率 |
*上記は、最低限の指標であり、独自の取り組みを開示することを妨げるものではない。
\ フォスターリンクの『HRシェルパ』は、貴社の人的資本経営への取り組みもサポートします /

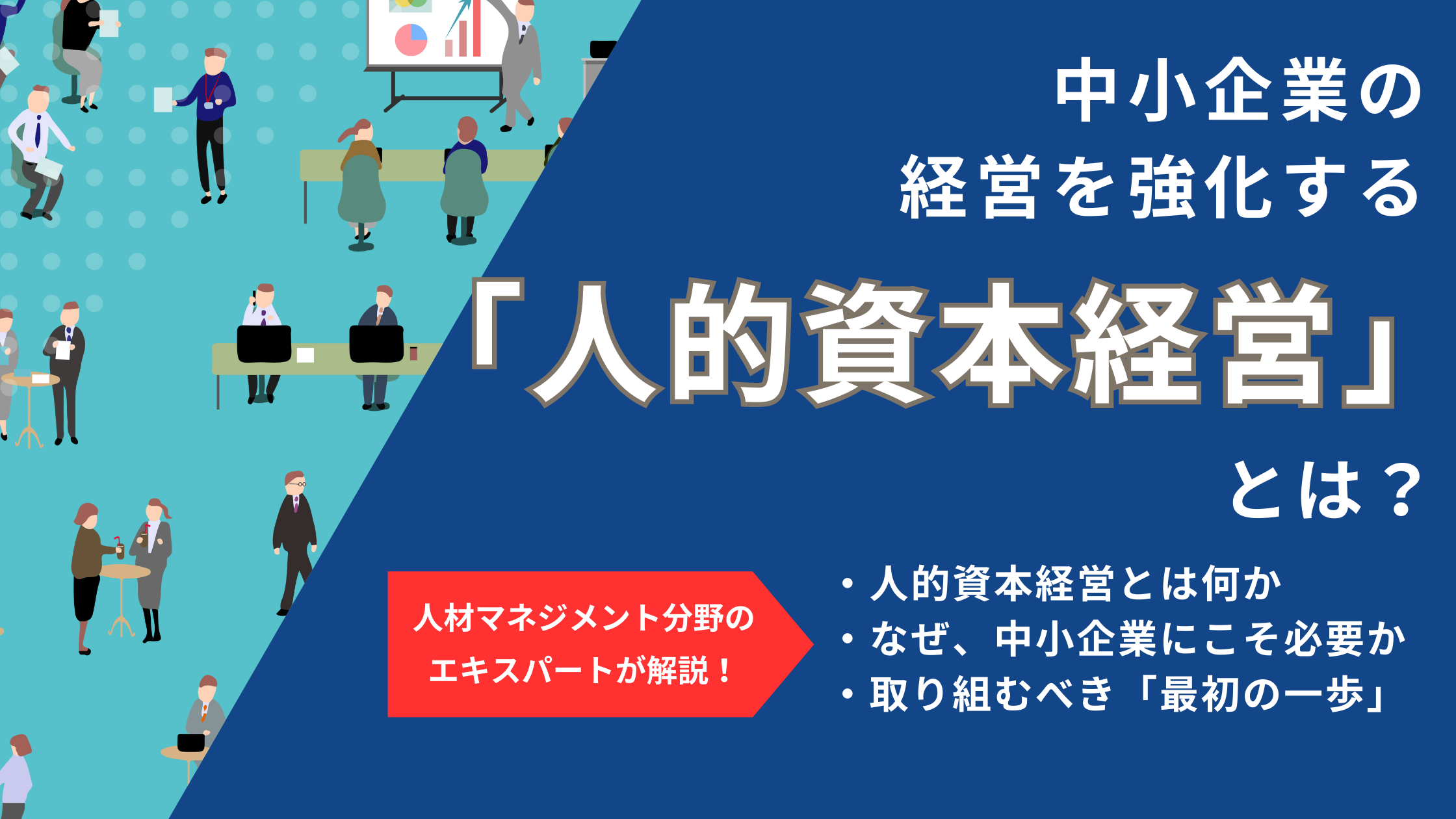
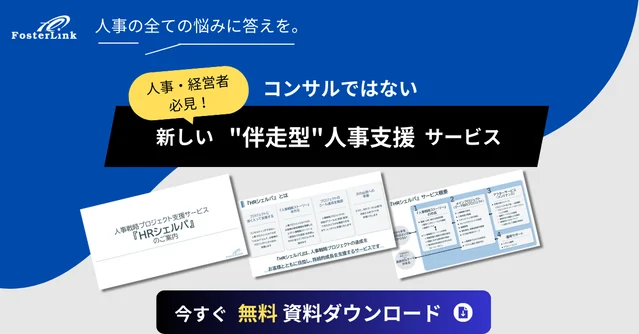
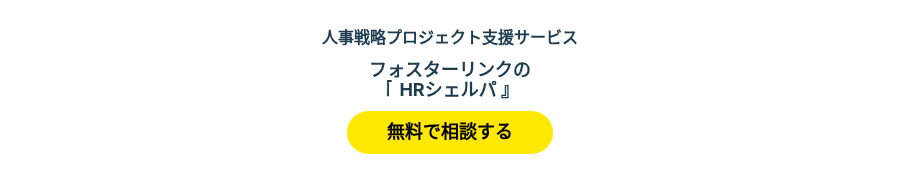
.png?width=624&height=427&name=%E5%AE%9A%E5%B9%B4%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%92%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97%20(1).png)
.png?width=624&height=427&name=%E3%83%9F%E3%83%89%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88_%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81%20(1).png)
.png?width=624&height=427&name=%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%9E%8B%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%20(5).png)