1.企業成長の鍵を握るミドルマネジメント人材
企業が持続的な成長を遂げるうえで、経営層と現場の橋渡し役となる“ミドルマネジメント層”は欠かせない存在です。
中間管理職、部課長職、プロジェクトリーダーなど呼び方は様々ですが、共通して言えるのは「経営の意図を現場に浸透させ、現場の声を経営に伝える」極めて重要な役割を担っているということ。
しかし現在、多くの企業がこの“ミドル”の人材不足、あるいは質の低下に悩んでいます。
「プレイヤーとしては優秀だが、マネジメントに向いていない」、「上からの指示をそのまま伝えるだけの“伝書鳩”にとどまっている」――このような課題を抱える企業は少なくありません。
では、有望なミドルマネジメント人材はどのように見つけ、育てればよいのでしょうか?
これまで、私は20年以上に渡り、会社を経営しながら組織・人事コンサルタントとしてクライアントの企業成長に携わってまいりました。
本記事では、企業経営者とコンサルタント両方の視点から、現場を動かす“真のミドル”の特徴を明らかにしつつ、実践的な発掘・育成方法を紹介します。
執筆者プロフィール
 倉島 秀夫 (くらしま ひでお)
倉島 秀夫 (くらしま ひでお)
1990年一橋大学経済学部卒業後、日本合同ファイナンス㈱(現ジャフコグループ㈱)入社
日本とアメリカでベンチャー投資業務に従事
1995年サンフランシスコにてPREMIO Inc. 設立(カリフォルニア法人)、取締役(現地経営責任者)に就任
PREMIO Inc.では日本人駐在員向けドル建てクレジットカードの発行とカード会員向けアメリカ生活総合支援サービスを提供
2000年に日本帰国、フォスターリンク㈱設立 代表取締役就任
フォスターリンクでは顧客企業の人事戦略立案から人事制度構築・運用まで幅広く支援している
2.ミドルマネジメントの役割とは?
まず、ミドルマネジメントの役割を明確にしましょう。
● 経営と現場をつなぐ「翻訳者」
トップが描くビジョンや戦略を、現場の言葉に置き換えて伝え、現場が実行可能なアクションに落とし込むことが求められます。
● チームを導く「リーダー」
プレイヤーではなく、部下を動かす存在。
部下の強みを活かし、目標達成へ導く力が必要です。
● 課題発見と改善を担う「現場改善者」
現場で生じる問題や非効率を見つけ、自ら動いて改善を図る。
いわば“現場の経営者”のような存在です。
これらの役割からもわかるように、ミドルマネジメントは単なる中間管理職ではなく、組織の要となる存在です。
トップの意図を正確に汲み取り、現場に適切に伝え、チームを率いて成果を出す。その一方で、現場の実情を把握し、課題を見極めて改善につなげる力も求められます。
経営と現場の橋渡し役として、ミドルマネジメントの質が、組織全体の成長スピードを大きく左右するといっても過言ではありません。
3.有望なミドルマネジメント人材の見極め方
多くの企業で陥りがちなのが、「年次」「スキル」「業績」だけでマネジメント候補を選んでしまうこと。
しかし、それだけでは本当に“チームを導ける”ミドルは見つかりません。
では、どのような視点で見極めればよいのでしょうか?
以下に、見極めのポイントと実務に役立つ見極めのヒントを具体的に解説します。
3-1.周囲を巻き込む力(インフルエンス)
部下だけでなく、他部署や上司ともうまく連携し、周囲を自然と動かせる力。
指示命令型ではなく、共感や信頼に基づく影響力を持つ人材です。
見極めのヒント:
- 会議での発言力ではなく「他者から頼られているか」
- チーム内で自然と相談が集まるタイプか
3-2.課題発見・解決志向
与えられたことだけをこなすのではなく、常に「どうすれば良くなるか」を考えて行動できる姿勢。
これは中長期的な視点でチームを導くために不可欠です。
見極めのヒント:
- 報告だけでなく「提案」もしているか
- ルールに従うだけでなく改善意識があるか
3-3.フィードバック力と育成意識
自分の業務遂行能力だけでなく、部下や後輩を育てようとする姿勢があるかどうか。
これがある人材は“チームの成長”に本気で向き合えます。
見極めのヒント:
- 若手との1on1やレビューで丁寧なフィードバックをしているか
- 自分以外の人の成果を喜べるか
これら3つの視点を通じて見えてくるのは、自分の成果よりも「チーム全体の成長」や「周囲への影響」を重視できる人材こそが、有望なミドルマネジメント候補であるということです。
年次や実績だけでなく、日常のコミュニケーションや立ち居振る舞いから“人となり”を丁寧に観察することが重要です。
企業の未来を担うキーパーソンを見極めるには、表面的な評価にとどまらず、現場のリアルな姿に目を向ける視点が求められます。
3-4.コーチャビリティ
「コーチャビリティ」とは、フィードバックを受け取る側に焦点を当てた考え方で、コーチングを受けることが出来たり、コーチングを受けた時に良い方向に機能しやすいといった意味合いの言葉です(英語で表記するとcoach+abilityでCoachabilityです)。
元々は、成功するスポーツ選手の資質としての概念でしたが、近年は仕事や組織においても取り入れられつつあります。
特に組織の従業員のコーチャビリティについては、その研究をしているWeissとMerriganの定義によると「個人の成長とパフォーマンス向上を促進するために、建設的なフィードバックを求め、受け入れ、実行する意欲と能力」とされています。
見極めのヒント
- 受動的ではなく、自分から自身の行動についての適切性などについて、フィードバックを求めて行動しているか
(フィードバック探索行動) - アドバイスに対して、まずは聞く耳を持とうとすること、それを咀嚼しようとすること、そして、必要に応じてそれを取り入れようとしているか
(フィードバック受容性) - フィードバックを受けた後にそれを反映して実際に何かしらの行動に移しているか
(フィードバックを反映した行動の実行)
▶「コーチャビリティ」の詳しい解説は、こちらの記事をご確認ください。
\ 経営者・人事担当者 必見人材育成の成果を最大化するヒントをこちらで無料配布中! /
4.有望なミドルマネジメント人材の見つけ方
では、前述したような特性を持つ人材をどのように見つけ出せば良いのでしょうか。
ここでは実際に使える発掘方法をいくつか紹介します。
4-1.1on1や目標面談を活用した“観察”
定期的な1on1や人事面談の中で、上司がただ話を聞くだけではなく、「この人はどんな視点で仕事を捉えているか」「チームをどう見ているか」に注目しましょう。
抽象的な言葉でなく、行動ベースで見極めることが大切です。
4-2.部門横断型プロジェクトへの抜擢
通常の業務とは異なるプロジェクトにアサインすることで、「マネジメントのポテンシャル」が露わになります。
他部門との調整力やリーダーシップは、通常のルーティン業務では見えにくいものです。
部門横断型プロジェクトに参画させることは、日常業務とは異なる環境下での行動や能力を観察する良い方法といえます。
4-3.マネジメント適性診断の活用
アセスメントツールを使った診断も有効です。
特に論理的思考力・対人感受性・意欲傾向など、マネジメントに必要な特性を科学的に測定できます。
4-4.周囲の評価を取り入れる(360度評価)
本人の自己評価だけでは見えない側面を、部下・同僚・上司などからのフィードバックを通じて把握します。
リーダー候補が「どう見られているか」を可視化することで、組織の納得感ある人選が可能になります。
▶ 企画から運用までトータルサポート!フォスターリンクの360度評価はこちら
5.ミドルマネジメント人材の育成方法
有望な人材は発掘して終わりではなく、育てることが不可欠です。
次に、育成のための具体的なステップをご紹介します。
STEP1:任せてみる(小さなリーダー経験)
いきなり部長や課長に登用するのではなく、まずは「小さなチームのリーダー」「プロジェクトのサブリーダー」などの役割を与えましょう。
現場でマネジメントを体感させることが、成長の第一歩です。
STEP2:フィードバックを与える
育成には“フィードバックの質”が決定的に影響します。成功・失敗の背景を共に振り返り、次に活かすサイクルをつくることが重要です。
本人任せにせず、必ず育成側が伴走してください。
▶「フィードバック」の詳しい解説は、こちらの記事をご確認ください。
STEP3:マネジメントスキルの体系的教育
部下の育成、評価制度の適切な運用、会議のファシリテーション、さらにはトラブル対応やメンタルケアといった領域は、ミドルマネジメントにとって不可欠なスキルです。
しかし、これらは単なる現場経験や自己流のやり方だけでは習得が難しく、属人的なマネジメントに陥るリスクもあります。
だからこそ、マネジメントスキルを再現性ある形で学ぶことが重要です。
外部の専門研修や、実務に即した社内講座を活用し、理論と実践をつなぐ体系的な教育機会を提供していきましょう。
それが、マネジメントスキルを底上げする鍵となります。
6.現場に埋もれている“ダイヤの原石”を活かす
多くの企業では、「実力はあるが、自己主張しない」「上昇志向は強くないが、チームに良い影響を与えている」――そんな人材が埋もれがちです。こうした“ダイヤの原石”を発掘・育成できるかが、企業の成長力を左右します。
そのために重要なのは、役職や成果だけを見ず、“日々の行動”と“周囲への影響”を見ていく視点です。
7. まとめ|未来を託す“現場のリーダー”をどう育てるか
ミドルマネジメント人材は、単なる管理職ではありません。
変化の時代において、現場を動かし、組織を変える“未来の中核人材”です。
有望なミドルマネジメント人材を見つけるためのポイントは、以下の通りです。
- 「プレイヤー能力」だけでなく「人を動かす力」に注目する
- 周囲からの信頼、育成志向、改善意識を見極める
- 発掘と育成をセットで行い、段階的に責任と権限を与える
- 表に出にくい“静かなリーダー”にも目を向ける
中間層が機能する組織は、どんな変化にも強く、長期的な安定成長を実現できます。
これからの人事戦略の中核に、ぜひミドルマネジメント人材の発掘と育成を位置づけてください。
\ フォスターリンクの『HRシェルパ』は、貴社のミドルマネジメント人材の発掘と育成もサポートします /

.png)


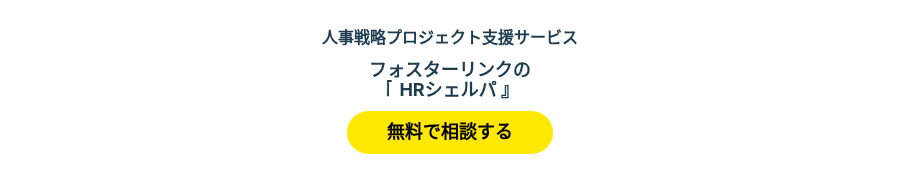

-1.jpg?width=624&height=427&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%20(1)-1.jpg)
.png?width=624&height=427&name=Navy%20Modern%20Isometric%20Recruitment%20Blog%20Banner%20(1).png)