お客様をご支援する中で、「良い人材が採れない」「内定辞退が相次ぐ」「採用コストが高騰している」
——こうした声が、多くの企業の現場から聞こえてきます。
少子高齢化、働き方の多様化、価値観の変化。これらが交錯する日本社会において、企業はかつてない採用難の時代に直面しています。
従来型の求人広告やリクルーター戦略だけでは限界がある中で注目されているのが、「人事制度」を軸とした組織・人事戦略の再構築です。
人事制度は、単なる給与や評価の仕組みではなく、「企業がどんな人材を求め、どのように成長を支援し、どんな未来を描いているか」を示す、極めて重要なメッセージでもあります。
本記事では、「人事制度を人材獲得競争の武器にするための考え方、設計ポイントから事例まで解説します
執筆者プロフィール
 倉島 秀夫 (くらしま ひでお)
倉島 秀夫 (くらしま ひでお)
1990年一橋大学経済学部卒業後、日本合同ファイナンス㈱(現ジャフコグループ㈱)入社
日本とアメリカでベンチャー投資業務に従事
1995年サンフランシスコにてPREMIO Inc. 設立(カリフォルニア法人)、取締役(現地経営責任者)に就任
PREMIO Inc.では日本人駐在員向けドル建てクレジットカードの発行とカード会員向けアメリカ生活総合支援サービスを提供
2000年に日本帰国、フォスターリンク㈱設立 代表取締役就任
フォスターリンクでは顧客企業の人事戦略立案から人事制度構築・運用まで幅広く支援している
1.採用難時代の現状認識と背景
まずは、現代の採用環境の背景を整理しましょう。
少子高齢化による労働人口の減少
日本の15~64歳の生産年齢人口は、1995年をピークに減少を続けており、今後も加速度的に減っていくと予測されています。これにより、特に若年層の採用競争は熾烈を極めています。

引用:厚生労働省 令和6年11月29日 第35回労働政策基本部会事務局提出資料
働き方の多様化
リモートワーク、副業、パラレルキャリアなど、「どこで・どう働くか」が個人に委ねられる時代になり、企業に属すること自体を選ばない人も増えつつあります。
ミスマッチの増加
労働市場における「量」だけでなく、「質」のミスマッチも問題です。厚生労働省の「新規学卒者の利殖状況」によると、ここ15年ほど31~32%で推移していた大卒者の就職後3年以内離職率は、令和3年に34.9%に上昇しています。企業が求める人材像と、求職者の志向性がすれ違うケースもみられ、入社後の定着率にも影響が出ています。
このような状況下では、いかに“選ばれる企業”になれるか、が問われています。
2.人材獲得の鍵を握る「人事制度」とは?
人材獲得 = ブランド × 制度 × 現場体験
人材獲得は、採用ブランディングだけでは不十分です。企業の価値を体現する人事制度と、日常的なマネジメントや育成の質が伴っていなければ、優秀な人材は定着しません。むしろ、制度の設計そのものが人材獲得競争の勝敗を左右すると言っても過言ではありません。
人事制度を「人材獲得の入り口」にする発想
従来、人事制度は「入社後の管理手段」として設計されていました。しかし、応募者に対する魅力訴求としての側面も求められるようになっています。「この会社なら成長できそうだ」と思ってもらえる人事制度の魅せ方が大切です。
たとえば以下のような点が、求職者にとって魅力的な情報になります。
• キャリアパスが明示されている
• 評価プロセスに透明性があり公平である
• スキルアップ支援が充実している
• ワークライフバランスを大切にしている
• 自律的な働き方が実現できる
3.人材獲得力を高める人事制度の設計ポイント
人事制度を人材獲得の武器とするために重要になるポイントを整理します。
ミッション・ビジョンとの一貫性
人事制度は、企業のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)と一貫していなければなりません。「何のために働くのか」「どんな価値を社会に提供するのか」を制度に落とし込むことで、理念に共感した人材を惹きつけやすくなります。
例:
• 「社会課題の解決」を掲げる企業が、プロボノ制度や社会貢献評価を導入している
• 「挑戦」を価値とする企業が、失敗に寛容な評価制度を取り入れている
キャリアの見える化と支援
採用面接において応募者からよく聞かれる質問に、「入社後どんな成長ができますか?」というものがあります。にもかかわらず、明確なキャリアフレームを提示できていない企業は多いのが実情です。
入社後にどんなキャリアステップを辿り、どう成長できるのかを応募者がイメージできる施策が必要です。
解決策:
- スキルマップや職種別キャリアパスの公開
- ロールモデルの紹介
- 資格取得・研修制度の整備と公開

引用:オリックス生命保険株式会社様 新卒/キャリア採用ページより抜粋
フェアで納得感のある評価制度
「評価が不透明」「上司の主観に左右される」といった不信感は、入社意欲にも悪影響を及ぼすのはもちろんのこと、入社後もエンゲージメントや定着率の低下を招きます。フェアな評価制度を設計することで、納得感と、組織に対する信頼感が高まります。
ポイント:
- 目標設定と評価基準を明確にする
- 上司だけでなく、360度評価など、多面評価を導入する
- 1on1など、定期的なフィードバック文化の醸成
柔軟な働き方の制度設計
現代の求職者は「報酬」だけでなく「働きやすさ」や「自由度」も重視しています。リモートワークや時短勤務、副業制度など、柔軟な働き方が可能な制度は大きな魅力となります。
導入例:
• 出社義務のないフルリモート制度
• ライフイベントに合わせたフレックス制度や柔軟な労働時間設定
• 副業解禁による社外スキル習得支援
4. 人事制度設計だけでなく“伝え方”も重要
魅力的な人事制度を整えたとしても、それが社外に十分に伝わらなければ意味がありません。コーポレートサイトや採用ページ、SNSなどの外部チャネル、実際に応募者と接する会社説明会や面接の場で「どのように自社の人事制度を伝えるか」が重要です。
コーポレートサイトや採用ページの強化
単に人事制度をわかりやすく伝えるだけでなく、実際に制度を活用している社員の声や、キャリアアップの成長事例を掲載することでリアリティを伝えることができます。
会社説明会や面接での丁寧な説明
会社説明会は、事業、職種説明や雇用条件などの説明だけでなく、自社のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)、さらに人事制度の背景や「なぜこの制度を設けたのか」といった企業の想いを語ることが、共感を呼ぶきっかけになります。
5. 事例:人事制度で人材獲得に成功した企業
株式会社A:スキル成長型等級制度の導入による応募の増加
業種:システムインテグレーター
規模:約1,000名
エンジニア採用に苦戦していたA社は、スキルベースの等級制度とスキル&コンピテンシーを評価項目とした評価制度を構築。
同時に、エンジニア職からマネジメント職にキャリアチェンジするための各種研修など、キャリア開発支援を整備、運用することにより、スキル志向の求職者からの応募の増加や、エンジニアの自律的なキャリア開発につなげた。
株式会社B:評価に“価値観”を組み込んだ制度による離職率の低下
業種:学術研究、専門・技術サービス業
規模:3000名以上
B社では、組織のバリュー(価値観)や行動指針を評価に組み込み、どういう姿勢や行動が評価されるのかを従業員に明示したことで、エンゲージメントが高まり、離職率が低下した。
採用活動においても、求める人材を明確に伝えていくことが採用におけるブランディングにつながっている。
6. 今後求められる“戦略的人事”の在り方
採用難は一時的なトレンドではなく、今後も続く構造的な課題です。だからこそ人事制度は、「経営戦略」として設計される必要があります。
• 自社が求める人材を惹きつけるための制度づくり
• 組織の文化を浸透させる評価・育成設計
• 多様な働き方に対応する就労制度
こうした「戦略的人事」を実現することで、企業は不確実性の高い時代においても、持続可能な成長を遂げていくことができるでしょう。
7.まとめ|人事制度は人を惹きつけ、人を育てる
採用難の時代において、企業が真に取り組むべきは「人事制度の見直し」ではなく「人事制度の進化」です。単なる雇用条件ではなく、企業の哲学や思想、ビジョンを体現するものとして、戦略的に人事制度を設計・発信していく。その姿勢こそが、優秀な人材を惹きつけ、共に未来を創っていく最大の武器となります。
人材獲得の第一歩として、いまこそ制度導入や見直しを真剣に検討してみてはいかがでしょうか。
フォスターリンクの「HRシェルパ」なら、経験豊富な専門家が貴社の確定拠出年金の導入もしっかり伴走して支援します。
▼「HRシェルパ」のくわしい内容については、こちらから無料ダウンロードできます。
▼支援実績20年以上!まずはフォスターリンクへお気軽にお問合せください。

.png)
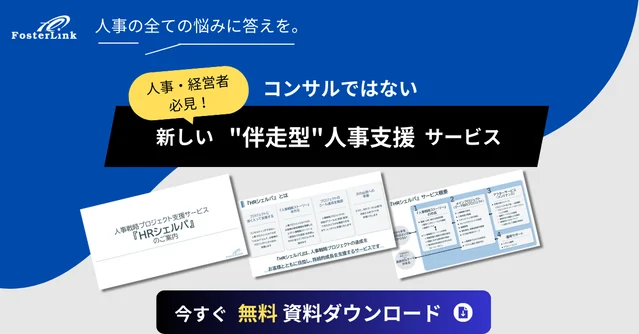
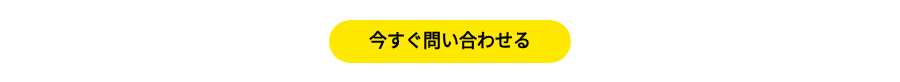


.png?width=624&height=427&name=%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%82%92%20%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%A7%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%20%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AF%20(1).png)