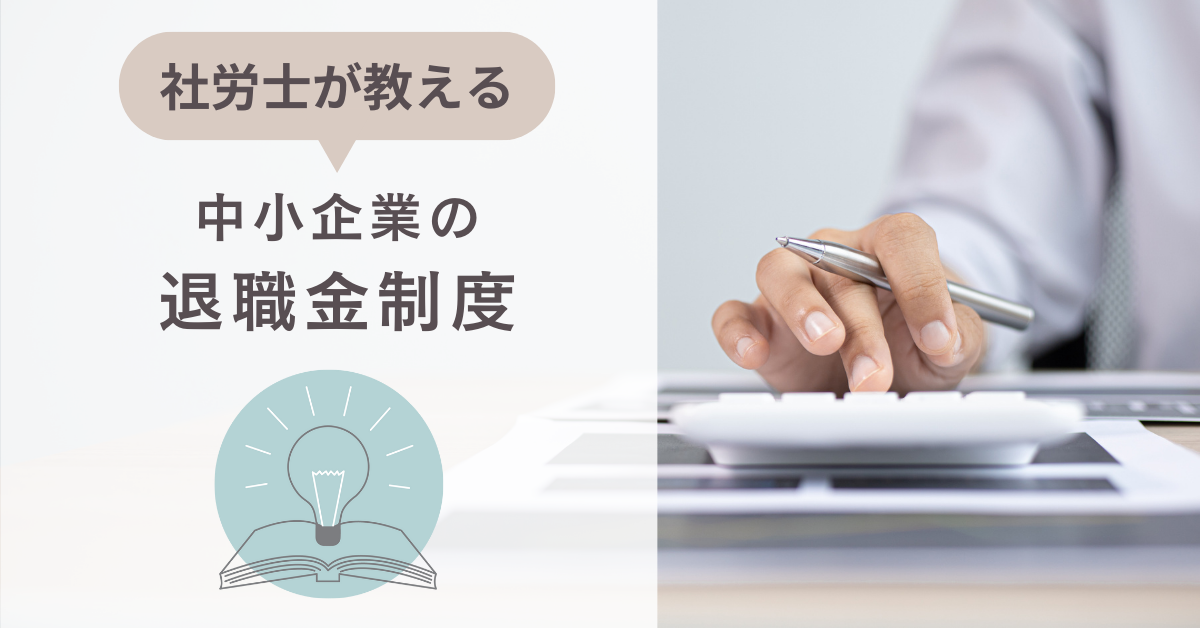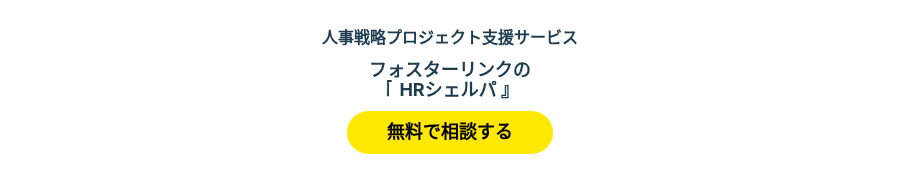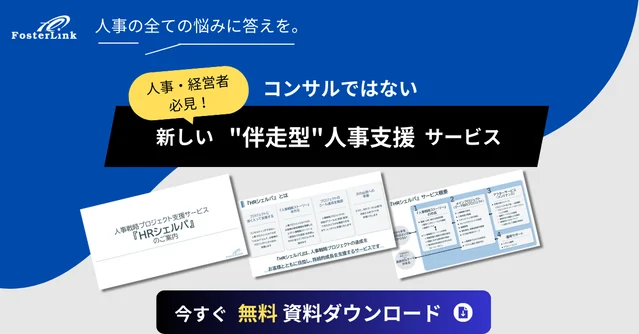働く人にとって、退職金は将来への安心を支える大切な制度です。しかし、特に中小企業では「退職金制度を設けるべきか迷っている」「他社の水準が分からない」「どんな制度が利用できるのか知らない」といった声が多く聞かれます。
本記事では、社労士の視点から、中小企業における退職金の現状と、制度導入のポイント、そして活用できる代表的な退職金制度について、詳しく解説します。
中小企業における退職金制度の実態
まずは、現在の中小企業における退職金制度の導入実態を見てみましょう。
退職金制度の導入率は約7割
厚生労働省の「就労条件総合調査(令和5年)」によれば、退職金(一時金・年金)制度がある企業割合は全体で74.9%となっています。
ただし、企業規模によって導入率は大きく異なります。以下は企業規模別の導入率です。
| 企業規模(人数) | 退職金制度の導入割合 |
| 1,000人以上 | 90.1% |
| 300~999人 | 88.8% |
| 100~299人 | 84.7% |
| 30~99人 | 70.1% |
小規模企業では退職金制度がない場合も多く、長期雇用へのインセンティブ不足や人材定着の課題に繋がることもあります。
中小企業における退職金の平均支給額は?
では、実際に中小企業ではどの程度の退職金が支給されているのでしょうか。
モデル退職金額(高校・高専/短大・大学卒モデル)
東京都産業労働局が令和4年に調査した結果によると、中小企業におけるモデル退職金額(※)は以下の通りです。
高校卒:9,741千円
高専/短大卒:9,920千円
大学卒:11,495千円
(※)学校を卒業してすぐに入社した者が、普通の能力と成績で勤務した場合の退職金水準を指す。

引用:東京都産業労働局 中小企業の賃金・退職金事情(令和4年)
一方で、大企業では30年以上勤続した社員に対し1,500万円以上の退職金が支給されるケースもあり、待遇格差が問題視されることもあります。
退職金制度がもたらすメリットとリスク
退職金制度があることによるメリットや注意したいリスクにはどういったものがあるのでしょうか。
ここでは、具体的な事例なども踏まえて解説していきます。
◆ 退職金制度によるメリット
1、人材の定着率向上
退職金は長く勤めるほど受け取れる金額が増えるため、社員の離職抑止につながります。
特に中小企業にとって、ベテラン社員の定着は業務の安定性や後進育成にも直結します。
 引用:中小企業退職金共済制度 加入企業の実態に関する調査報告書(2022年)
引用:中小企業退職金共済制度 加入企業の実態に関する調査報告書(2022年)
実際に、中小企業退職金共済制度に加入している企業を対象とした2022年度の調査によると、約35%が退職金制度による従業員の定着率やモチベーションの向上を実感する結果となっていることがわかります。
2、優秀人材の採用に有利
求職者は待遇の安定性を重視しており、退職金制度の有無は求人応募に大きな影響を与えます。
特に大企業との待遇格差を感じさせない施策として有効です。
東京都のあるIT企業では、新卒・中途採用の応募数が伸び悩んでいました。
そこで、福利厚生の充実を目的に「企業型確定拠出年金(DC)」を導入。求人票には「退職金制度あり(DC)」と明記しました。
その結果、求職者からの注目度が高まり、応募数は前年の約2倍に増加。採用の質も向上し、より自社にマッチする人材の確保につながったという事例も見られます。
3、経営者の退職資金対策にも有効
退職金制度は従業員向けのものだけでなく、経営者本人にも適用できる制度があります。
節税しながら退職後の生活資金を準備できるという点も、退職金制度を導入する大きなメリットの一つと言えます。
◆ 退職金制度によって生じ得るリスク
1、将来的な資金負担
自社制度(内部積立型)の場合、退職者が出た際に数百万程の支払いが一度に発生することもあります。
制度設計を誤ると経営を圧迫する可能性があることも念頭に置いておく必要があるでしょう。
そうしたリスクを事前に回避するためにも、どういった制度をとるべきか、その運用方法等についても詳しく専門家と協議の上決定しておくべきです。
2、制度運用の不備によるトラブル
退職金規程が不明確であったり、就業規則と矛盾していると、トラブルにつながります。
また、支給の有無や金額に一貫性がないと不公平さを訴えられる可能性も生じます。
導入の際には、就業規則との整合性をはかる、運用ルールを明確にする、退職金規程を整備するなどの手順が必要です。
3. 財務上の見えないリスク「退職給付債務」
退職給付債務とは、将来従業員に支払う予定の退職金を企業の隠れた負債として見積られたものです。
制度設計や運用を誤ると、将来的に資金繰りを圧迫する原因となり、企業の財務リスクとして大きな課題になります。
このリスクを回避・軽減するためには、以下のような対策を講じることが重要です。
- 外部積立型制度の導入
- 退職金規程・制度の明文化と上限設定
- 会計上の退職給付引当金の適切な積立と管理
- 早期退職制度や段階的退職金の導入
- 定期的な制度見直しとシミュレーションの実施
企業規模や人員構成、財務状況に応じて、複数の対策を組み合わせて取り入れることが現実的な対策となります。
中小企業が活用しやすい退職金制度
中小企業において、手軽に導入・運用できる退職金制度としては次の3つが代表的です。
中小企業退職金共済制度(中退共)
中小企業退職金共済制度とは、中小企業が単独で退職金制度を設けることが難しい場合に、国が運営する外部積立型の退職金制度です。事業主が毎月掛金を納付し、従業員が退職した際に、中小企業退職金共済事業本部から退職金が支払われます。
掛金は月額5,000円〜30,000円(500円単位)から事業主が自由に選択可能です。
短時間労働者(パートタイマー等)については、2,000円~4,000円で1,000円ごとに選択ができます。
| メリット | デメリット |
| ・掛金全額が経費扱い(税制優遇あり) ・国からの掛金助成がある(新規、増額分) ・個別管理が不要なので、事務負担が少ない |
・柔軟な制度設計(評価連動等)が難しい ・原則として途中解約ができない |
以上のような特徴から、人材流動性の高い業態や業種、事務負担を軽減したい小規模事業者などにおすすめの制度とも言えます。
確定拠出年金(企業型DC)
確定拠出年金(企業型DC)とは、毎月の掛金を企業が拠出し、従業員が自己運用する制度を指します。
原則として60歳以降に年金 または 一時金として受取ることが可能です。
| メリット | デメリット |
| ・拠出金が税金の控除対象となる(税制優遇) ・運用次第で受取額を増やせる |
・運用リスクを従業員が負担する必要がある ・導入時金融機関との契約・説明義務などが必要 |
運用責任を従業員が負うため、確定拠出年金はしっかりとした制度への理解と制度設計が必要となります。
そのため、若手社員が多く、長期的な運用を見込むことができる企業や、IT・金融業など投資リテラシーが高い業種になじみやすい制度とも言えるでしょう。
また、比較的経営体力があり、資産形成支援を重視したい企業にとっても人気のある制度です。
小規模企業共済(経営者・役員等向け)
最後の小規模企業共済とは、従業員ではなく中小企業の経営者や役員、個人事業主を対象とした制度です。
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
| メリット | デメリット |
| ・掛金は全額所得控除の対象(税制優遇) ・共済金は退職後の生活資金や事業承継資金に活用可能 |
・原則として途中解約は損失が出る場合あり ・掛金の一部を引き出すことはできない ・長期加入が前提となる |
自己資産を守りつつ、将来の退職や廃業に備える手段としておすすめの制度の一つと言えます。
中小企業向け退職金制度の導入方法

中小企業が退職金制度を導入する際は、以下のようなステップで進めることが効果的です。
STEP1:目的と対象者の明確化
まず大切なのは、「何のために退職金制度を導入するのか」という経営側の目的の明確化です。
一例としては、以下のような目的が考えられます。
・人材定着を図りたい(長期雇用のインセンティブ)
・採用力を強化したい(待遇の魅力強化)
・従業員の老後資金を支援したい
・経営者自身の退職金を準備したい
この目的をまずは明確化することによって、制度の設計や運用方針をぶらさずに作っていくことができます。
また、目的が定まったら、次にすべきことは対象者を確定させることです。
正社員のみか、契約社員やパートも含めるかどうか。
入社後すぐに加入対象にするか、数年後から対象にするか、等の要件を固めていきましょう。
STEP2:制度の選定と試算
次に、目的や社内体制に応じて、取るべき制度や組み合わせを選定します。
上述した中小企業退職金共済制度、確定拠出年金、小規模企業共済以外にも、自社内で策定する退職金制度や生命保険型の退職金制度なども多数制度は存在します。
会社全体で毎月いくら負担するか、退職時にどれだけの支出が想定されるかを予測しながら掛金をシミュレーションしていくことが必要となります。
STEP3:就業規則・退職金規程の整備
退職金制度を導入する際は、労働条件の一部として就業規則または退職金規程に明記する必要があります。
また、常時10人以上の労働者がいる事業場では、労働基準監督署への届け出が必要です。
記載すべき内容例としては、以下のような項目が考えられます。
・対象者の範囲(正社員のみ、勤続〇年以上など)
・支給の条件(退職理由による差など)
・計算方法(勤続年数・基本給に基づくなど)
・不支給となる場合(懲戒解雇等)
専門家の知見も取り入れながら、法令に沿った内容に整備していきましょう。
STEP4:従業員への説明と運用開始
導入後は、必ず従業員説明会や資料配布を行い、制度の概要と目的をしっかり伝えることが大切です。
説明の仕方次第で、制度への信頼度が大きく変わります。
また、掛金の管理方法や制度に関する問合せ窓口も定めると共に、定期的な見直しとメンテナンスも忘れずに行っていくことが重要です。
まとめ | 退職金制度は“攻め”の人材戦略
退職金制度は「コスト」と捉えられがちですが、うまく設計すれば「人材定着」「優秀人材の確保」「経営者の資産形成」にも貢献する、“攻め”の人事制度となります。
中小企業にとっては、手軽に始められる制度から導入することが現実的であり、中退共や小規模企業共済といった公的制度を活用することで、負担を抑えつつ安心できる仕組みを整えることが可能です。
フォスターリンクの人事戦略プロジェクト支援サービス『HRシェルパ』では、退職年金制度の構築支援も行っています。
「退職金制度を導入すべきか迷っている」「他社事例が知りたい」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
参考文献
- 厚生労働省『就労条件総合調査(令和5年)』
- 東京都産業労働局『中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)』
- 退職金制度の教科書 制度の全体像をとらえ今後の設計・運用を考えるために/秋山 輝之 (著)【2016】