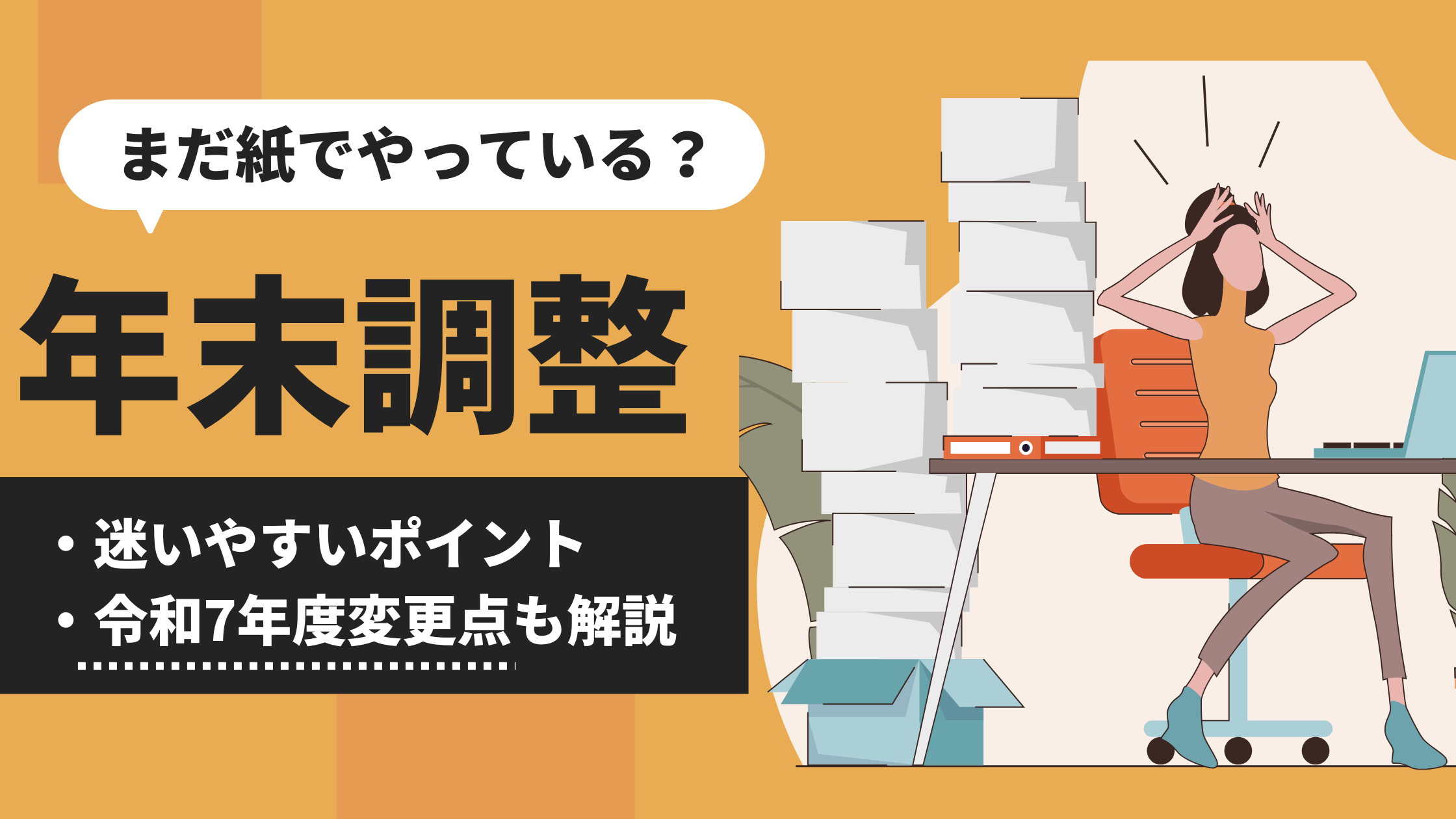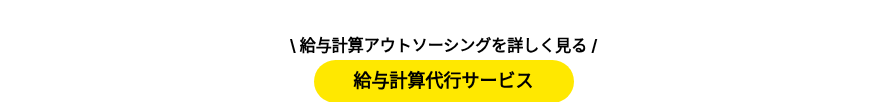年末調整業務は、人事・経理担当者にとって「毎年必ず訪れる大仕事」です。短期間に大量の書類を回収・確認し、正確に処理する必要があるため、担当者の年末年始の負担は非常に大きなものになります。
さらに忘れてはならないのが、年末調整は単体の業務ではなく、その後に続く法定調書作成や給与支払報告書の提出まで含めた一連の処理であるという点です。
これらをすべて期限内に終えなければならず、少しの遅れや不備が従業員や自治体への対応遅延、さらにはコンプライアンスリスクにつながることもあります。
本記事では、年末調整から給与支払報告書提出までの業務全体像を整理し、迷いやすいポイントなど、実務に役立つヒントをご紹介します。「毎年この時期になるとバタバタしてしまう」「紙ベースの運用に限界を感じている」といった課題をお持ちの企業様にとって、少しでも負担を軽減するための参考になれば幸いです。
1.年末調整の概要
1-1.年末調整とは
年末調整とは、給与から源泉徴収された所得税を、その年の給与総額について納めなければならないの本来の年税額に合わせて精算する手続きです。
給与所得者の場合、毎月(毎日)の給与や賞与から所得税が概算で天引きされています。しかし、その計算は扶養状況や保険料控除などを十分に反映していないため、年末の時点で その人の1年間の給与総額と各種控除額を正しく反映し、納めるべき税額を再計算する必要があります。
年末調整を行うことで
源泉徴収額が 多すぎた場合 → 還付
源泉徴収額が 少なすぎた場合 → 追徴
が行われ、最終的にその年の所得税が確定します。
1-2.年末調整の流れ
主な流れは以下のとおりです(詳しくは第3章で説明します)
① 従業員から各種申告書を提出してもらう
- 当年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等(異動)申告書」。)
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書
- 来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 など
※その他、必要に応じて上記に付随する添付書類を提出します。
② 会社(給与支払者)が計算・精算を行う
→ 年末(通常12月給与支給時)に、源泉徴収済みの所得税額を調整します。
③ 翌年1月に法定調書・給与支払報告書を提出
→ 副業や別収入があるなど、従業員個人で確定申告が必要なケースがあります。
年末調整を行うことによって、従業員は正しい税額を確定することができます。企業は源泉徴収義務を果たすことで税務コンプライアンスを担保する、非常に大切な手続きです。
2.年末調整の対象
2-1年末調整の対象となる人、ならない人
年末調整は、原則として企業に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が対象になります。
しかし、その中でも例外的に対象にならない人がいます。対象にならない人は、各自が住所地の所轄税務署長に確定申告をする必要があります
| 対象となる人 |
次のいずれかに該当する人 |
| 対象とならない人 |
次のいずれかに該当する人 |
2-2.年末調整をするタイミング
年末調整はその年最後に給与の支払いをする時に行いますので、通常は12月に行いますが、以下に該当する人は、それぞれ次の時に年末調整を行います。
| 年末調整の対象となる人 | 年末調整を行う時 |
| ⑴ 年の中途で死亡により退職した人 | 退職の時 |
| ⑵ 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時 期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人 | 退職の時 |
| ⑶ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 | 退職の時 |
| ⑷ パートタイマーとして働いている人などが退職した場合 で、本年中に支払を受ける給与の総額が、123万円以下である人 (退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。) |
退職の時 |
| ⑸ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居者となった人 | 非居住者となった時 |
参考:国税庁令和7年分年末調整のしかた:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
3. 年末調整から給与支払報告までの流れ
年末調整業務は「12月に行って終わり」ではありません。実際には翌年1月末まで続く一連の処理として捉える必要があります。ここでは、担当者が対応すべき代表的なステップを整理します。
①申告書類の配布と申告
- 申告書類を対象者に配布
- 従業員が、申告書類を記入、保険控除証明書など必要書類を添付して提出
②申告書類等の回収とチェック
- 従業員からの申告書類、添付書類を回収。未提出の督促
- 記入漏れや証明書との整合性など、チェック。必要に応じて修正や再提出依頼
※紙で運用している場合、記入漏れや証明書の紛失が頻発し、確認作業に大きな時間を取られます。
③年末調整計算
- 確定した控除内容を給与計算システムに反映し、源泉徴収税額を再計算
④法定調書作成/提出
- 以下の書類を作成し、期日までに税務署に提出
源泉徴収票/支払調書/法定調書合計表 - 給与支払報告書を、各従業員の居住地市区町村ごとに提出(翌年1月末まで)
※市区町村によってフォーマットや提出方法(紙・電子)が異なる - 従業員に源泉徴収票を交付(翌年1月末まで)
このように、年末調整は年をまたいで続く「連続した業務」であり、1つの処理が遅れると次の工程に影響を及ぼすリスクがあります。
4.迷いやすい点・手間がかかる要因
年末調整から給与支払報告書までの業務は、流れとしては定型化されています。
しかし実際のチェック作業などにおいては担当者を悩ませるポイントや手間のかかる処理が数多く発生します。
ここでは代表的な負担ポイントを整理します。
4-1.従業員からの提出漏れ・不備対応
従業員が申告書や控除証明書を期日までに提出してくれない、扶養控除申告書に記入漏れがある、マイナンバー記載の不備など、担当者は督促や差し戻しを繰り返す必要があり、最終的に処理期限が迫るほど負担が増大します。
4-2.法改正への対応
住宅ローン控除や扶養控除の細かい要件変更や、控除額や申告書様式の変更など、法令改正の内容を正しく理解し、従業員に説明・周知する必要があり、担当者が毎年キャッチアップに追われます。
令和7年度の変更点については、次の章にまとめています
4-3.中途入社者の処理
例えば10月や11月に入社した従業員の場合、前職分の源泉徴収票を回収し、合算して年末調整を行わなければなりません。
前職の源泉徴収票がなかなか提出されなかったり、金額の整合性が取れずに従業員と確認が必要だったりすると、処理の遅れの要因となります。
4-4.甲欄・乙欄の変更
年の途中で「甲」・「乙」が変更となった場合には、変更経緯(副業等)や最終的に甲・乙どちらなのかなどによって、年末調整対応が可能な場合・確定申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
4-5.高額所得者の対応
給与収入が2,000万円を超える従業員については、年末調整の対象外となり、自身で確定申告を行う必要があります。
ただし担当者は「年末調整をしない旨」を従業員に説明し、給与支払報告書などは提出しなければならないため、ケース分けや説明対応に時間がかかります。
4-6. 提出フォーマットの煩雑さ
給与支払報告書は市区町村ごとにフォーマットが異なり、紙申告の場合には封入・発送作業だけでも膨大な工数となります。 (eLTAX(電子申告)への切り替えを推奨)
4-7. 属人化とリソース不足
以上のように大変煩雑であり、しかも年に一度しかない業務のため、担当者の負担は小さくありません。また、個人情報を扱う業務のため、限られた担当者で行うケースが多く、もしもベテラン担当の退職・異動などが発生した場合の業務負担やリスクは想像以上のものになります
5.【要チェック!】令和7年度 変更点
国税庁からの案内によると、令和7年度も、以下のような所得税の基礎控除の見直し等があります。
① 基礎控除の見直し
これまでは、合計所得金額に応じて一律48万円だったのが、合計所得金額に応じて58〜95万円に段階的に引き上げ
(注)
1) 改正後の所得税法第 86 条の規定による基礎控除額 58 万円に、改正後の租税特別措置法第 41条の 16 の2の規定による 加算額を加算した額となります。
2) 58 万円にそれぞれ 37 万円、30 万円、10 万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者について のみ適用があります。
3) 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4) 合計所得金額 2,350 万円超の場合の基礎控除額に改正はありません
改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前(令和7年まで)の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税 額との精算を行う必要があります。
※基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
② 給与所得控除の引き上げ
これまでの55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。

(注) 給与の収入金額 190 万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません
年末調整では、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算した上で、改正前(令和7年まで)の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行う必要があります
※給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
③ 特定親族特別控除の新設
- 「特定親族」がいる場合に、最大63万円の控除が受けられる制度を新設
- 特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得が58万円超123万円以下の人を指します。ただし、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。
- 控除額は所得区分に応じて以下の9段階に設定されている

- 適用を希望する場合、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要
④ 扶養控除・配偶者控除などの所得要件の引き上げ
- 扶養親族や同一生計配偶者の所得上限が「48万円以下」→58万円以下(給与収入では約123万円以下)に緩和
- 勤労学生控除の所得上限も「75万円以下」→85万円以下へ引き上げられ、学生の働き方の柔軟性に対応
この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族がいる場合には、扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となるので注意が必要です。
6. 業務効率化の具体的手法
年末調整から給与支払報告までの一連の業務は、煩雑かつ期限が厳格に定められています。そのため、担当者が自力で抱え込むのではなく、システム化や仕組み化によって「人の手作業を減らす」ことが効率化の鍵となります。ここでは代表的な手法を紹介します。
6-1. システム活用による効率化
年末調整のクラウドサービス等を活用すると、従業員自身がWeb上で必要事項を入力・添付できます。担当者は入力内容を一元的に確認できるため、書類不備や二重チェックの手間が大幅に削減されます。
書類回収もオンライン化されるので、提出状況をリアルタイムで確認でき、督促も自動リマインドで行えるため、担当者が一人ひとりに連絡する負担が減ります。
また、生命保険料控除証明書や住宅ローン控除証明書をマイナポータル経由で取得することで、従業員の証明書提出の負担も軽減可能。電子申告と合わせれば、紙の提出業務も最小化できます。
6-2.チェックリスト整備と標準化
提出書類や期限管理をチェックリスト化し、毎年同じ流れで進められる体制を整えることが重要です。
標準化によって、属人化リスク低減することにもつながります
7. アウトソース活用のメリット
前章で述べたような対応をすることで、一定の効率化の実現はできるものの、大きな負担がかかる業務であることには変わりがなく、属人化のリスクも完全に回避できるものではありません。
こうした状況を根本的に改善する手段のひとつが「アウトソース」の活用です。専門事業者に任せることで、以下のようなメリットを得られます。
7-1.最新法令への確実な対応
年末調整では毎年のように控除制度の改正や様式の変更が発生しますが、アウトソースを活用すれば、専門家が最新法令に基づき処理を行うため、法令遵守の安心感があります。
また、経営者にとっても「コンプライアンスリスクの低減」につながります。
7-2.専門家によるチェックでミス防止
第4章で述べたように、担当者が迷ったり悩んだりするポイントが数多くある年末調整ですが、専門家に任せることによって高精度なチェックが実現できます。
7-3.業務ピーク時の負担軽減
年末調整業務は11月から1月末にかけて短期間で集中します。
繁忙期をアウトソースに任せることで、担当者の残業や休日出勤を削減でき、人的リスクやメンタル負担も軽減されます。
7-4.担当者のリソースをコア業務へ集中
自社で年末調整を行うと、担当者は不備対応・システム入力・市区町村提出書類の作成などに追われ、本来注力すべき人事戦略や採用活動が後回しになりがちです。アウトソースを活用すれば、担当者の時間を戦略業務へシフトでき、会社全体の生産性向上に直結します。
年末調整を単なる“事務作業”と捉えず、「外部リソースを活用して、会社の人材をより付加価値の高い業務に振り向ける」という視点が、経営における重要な判断材料となります。
8.まとめ|年末調整を紙で運用している企業はご検討を
年末調整から給与支払報告書の提出までは、毎年必ず発生する定型業務です。しかし、その業務量は膨大で、制度改正や提出先の多様性も加わり、担当者にとって大きな負担となっています。
「今年はまだ紙で回収している」「担当者が毎年疲弊している」という企業は、まずは自社の現状をチェックし、システム導入やアウトソース活用を検討することをおすすめします。
フォスターリンクでは、給与計算・年末調整から給与支払報告書対応までの業務を、アウトソーシングいただけます。専門の担当が正確かつ迅速に処理することで、担当者様の事務負担を大幅に軽減し、ミスや遅延のリスクも抑制可能です。
また、単なる代行にとどまらず、現行フローをご確認させていただき、業務効率化やコスト削減につながる改善点を明確化いたします。
最適な運用スキームをご提案することで、経営資源をコア業務へ集中できる環境づくりをサポートいたします。貴社の人事・労務体制をより強固かつスマートに進化させるパートナーとしてご活用ください。
\ フォスターリンクの給与計算アウトソーシングサービス 資料ダウンロードはこちら /
9.参考文献
厚生労働省 令和7年度 年末調整のしかた:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm