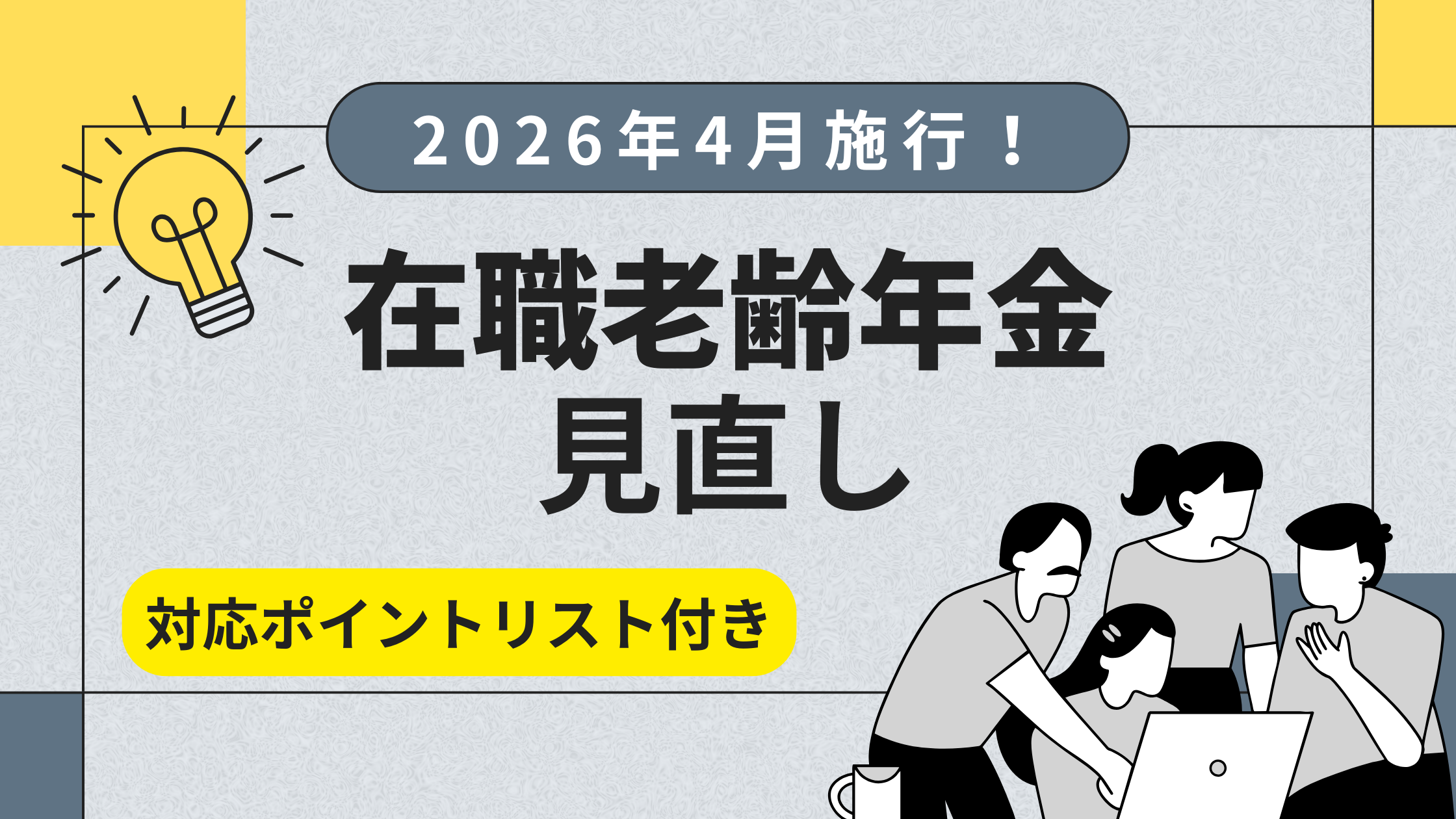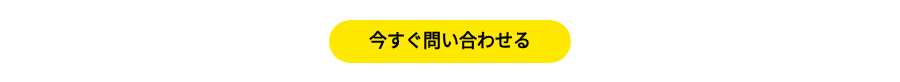2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が「月額50万円(2024年度価格) 」もしくは「月額51万(2025年度価格)」 」から「月額62万円」へと引き上げられることが予定されています。
これは、年金制度改正の中でも高齢者の就労に直結する重要な改正であり、企業の人事労務担当者にとっても実務対応が求められる変化です。
本記事では、この改定の概要と、実務ポイントをわかりやすく解説します。企業様にとって、少しでも負担を軽減するための参考になれば幸いです。
1.制度改正の背景と企業への影響
1-1.高齢者の就労意欲と労働力人口の現状
日本では少子高齢化が進み、労働力人口の確保が喫緊の課題となっています。総務省の統計によると、65歳以上の労働力人口は930万人と過去最多を記録しており、今後も増加見込まれます。

引用:総務省 労働力調査 2024年
さらに、内閣府の「高齢社会白書」では、現在収入のある仕事をしている60歳以上の者については約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答しており、70歳くらいまで又はそれ以上との回答と合計すれば、約9割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえる、という見解が記されています。

引用:内閣府 令和6年版高齢社会白書
企業にとって高齢者の活用は避けて通れないテーマとなっています。
1-2.「働き損」解消に向けた制度改正
一方で、年金制度では、60歳以降も働く人が一定以上の収入を得ると、在職老齢年金の一部または全部が支給停止となる、いわば「働き損」状態が生じていました。
この影響は、働き方の選択につながります。厚生労働省の調査によると、「厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方」について、44.4%の人が「年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く」と回答しています。

引用:内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」(2024年)
実際に、支給停止対象者は約50万人、支給停止額は年間約4,500億円にのぼるとされており、就労意欲を削ぐ要因となっていました。
こうした状況を改善するため、今回の改正では支給停止基準額が月額62万円に引き上げられる見通しであり、支給停止対象者は約30万人に減少、支給停止額も約2,900億円に縮小される見込みです。
これは、高齢者が年金を受け取りながら働きやすくなる環境整備の一環であり、企業にとっても人材確保のチャンスとなります。
65歳以上の老齢厚生年金の支給停止の状況

引用:厚生労働省 年金制度改正の全体像
2.制度改正の具体的内容
2026年4月施行予定の在職老齢年金制度改正では、支給停止基準額が「月額50万円(2024年度価格)」もしくは「月額51万円(2025年度価格)から「月額62万円」へと引き上げられる見通しです。これは、60歳以降も働く人が受け取る厚生年金の支給額に直接影響する重要な変更です。
これまでの制度では、60歳以降の在職者が「基本月額(年金)+総報酬月額相当額(給与)」の合計が50万円(2025年度価格の場合は51万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となっていました。
今回の改正では、この基準額が月額62万円に引き上げられることで、より多くの高齢者が年金を受け取りながら働けるようになります。

引用:厚生労働省 年金制度改正の全体像
| 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額 総報酬月額相当額: (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12 ※上記の「標準報酬月額」、「標準賞与額」は、70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。 |
引用:日本年金機構ウェブサイト
3.企業に求められる対応
在職老齢年金の支給停止基準額引き上げは、企業にとって「高齢社員の働き方を見直す好機」であると同時に、「制度対応の準備が必要なタイミング」でもあります。
企業は高齢社員の定年再雇用制度・嘱託規定の再確認、報酬設計や、就労時間の見直し、人件費への影響検討、制度説明の強化など、多岐にわたる実務面での対応が求められます。
人事労務担当者は、制度改正の趣旨を理解したうえで、社内制度や実務運用の見直しを進めることが求められます。
- 定年再雇用制度・嘱託規定の再確認:年金支給額と給与のバランスを考慮した設計が必要
- 制度説明の強化:従業員への丁寧な情報提供と相談対応
制度改正は、企業の人材戦略や働き方改革にも影響を与える重要な転換点なのです。
企業が高齢者の活躍を支援する姿勢を示すことは、採用力や職場の心理的安全性向上にもつながります。
3-1.報酬設計等の見直しや、人件費への影響検討
支給停止基準額が引き上げられることで、これまで「年金が減るから」と就業時間を抑えていた高齢社員が、フルタイム勤務や報酬増加を選択しやすくなります。企業側も、報酬設計や就労時間の柔軟な選択肢を提示することで、経験豊富な人材の活用を促進できます。
- フルタイム復帰の選択肢提示
- 職務内容や責任に応じた報酬体系の再設計
- シニア向けキャリアパスの整備
3-2.定年再雇用制度・嘱託規定の再確認、雇用契約の見直し
ただ単に勤務時間の増加を希望する対象者を受け入れるのではなく、企業が希望する人材を適切確保するために、現状の再雇用制度や嘱託規定の再確認が必要です。
また、 報酬体系や就労時間の変更に伴い、雇用契約書の内容も見直しが必要になる場合があります。
- 定年後再雇用制度・嘱託規定の再確認
- 雇用契約書の更新(報酬・勤務時間の変更反映)
3-3. 制度説明と従業員対応の強化
制度改正は、従業員にとっても不安や疑問が生じやすいテーマです。特に年金と給与の関係は複雑で、誤解を招きやすいため、企業側からの丁寧な情報提供が不可欠です。
- 制度改正の概要をわかりやすく説明する資料の作成
- 個別相談の場の設置(社労士との連携も有効)
- FAQの整備と社内ポータルでの共有
4.実務対応のチェックポイントリスト
制度改正に向けた準備は、情報共有だけでなく、社内制度・運用・システムの見直しまで多岐にわたります。人事労務担当者がスムーズに対応を進めるためには、対応項目を整理し、優先順位をつけて着実に進めることが重要です。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度改正の概要を社内で共有したか | 経営層・人事部門・現場責任者への情報展開 |
| 該当社員の報酬・就労状況を把握したか | 60歳以上の社員の給与・勤務時間を確認 |
| 支給停止基準額変更による影響を試算したか | 年金支給額と給与のバランスをシミュレーション |
| 社労士・外部専門家への相談を実施したか | 制度対応の妥当性確認とリスク回避 |
| 該当社員への説明資料を作成したか | 制度改正の背景・影響・選択肢を明示 |
| 勤怠・報酬設計の見直しをしたか | フルタイム勤務や報酬増加の選択肢提示 |
| 各規定・制度の再確認 ・雇用契約書の改訂などに対応したか | 再雇用制度や短時間勤務制度との整合性 |
| 人材管理クラウドとの連携を確認したか | 年齢・報酬・年金情報の一元管理体制 |
| さらなる改正への備えを検討したか | 中長期的な制度設計の視点を持つ |
5.制度改正をチャンスに変える企業の視点
在職老齢年金の支給停止基準額引き上げは、単なる制度変更ではなく、企業にとっては「高齢人材の活用を再設計する絶好の機会」です。人手不足が深刻化する中、経験豊富な高齢社員の力を最大限に活かすことは、企業の持続的成長に直結します。
5-1.制度改正を「攻めの人材戦略」に活かす
これまで「働き損」を避けるために就業時間を抑えていた高齢社員が、制度改正によってフルタイム勤務や報酬増加を選択しやすくなります。企業側も、柔軟な働き方や報酬体系を提示することで、シニア人材の定着・活躍を促進できます。
- シニア層の再戦力化による生産性向上
- 若手社員との知見共有による組織学習の促進
- 多様な働き方の選択肢提示によるエンゲージメント向上
5-2.今後の制度改正にも備える視点
今回の改正は「第一歩」に過ぎません。政府は将来的に、さらなる改正案を検討しています。企業としては、今後の制度変更にも柔軟に対応できるよう、中長期的な人事制度設計が求められます。
- 制度変更を前提とした報酬設計の柔軟性確保
- 高齢者雇用に対応した就業規則の整備
- 外部専門家との連携による制度設計支援
5-3.制度対応は「コスト」ではなく「投資」
制度改正への対応は、単なる事務作業ではなく、企業の人材戦略を強化する「投資」です。給与計算や人材管理のアウトソース、クラウド活用、制度設計支援などを通じて、社内リソースを効率化しながら、より戦略的な人事運営が可能になります。
6.まとめ|今すぐできることからはじめよう
制度改正は2026年4月に施行される予定ですが、準備は早ければ早いほどスムーズに進みます。
まずは制度の概要を正しく理解し、該当社員の状況を把握することから始めましょう。
今回の改正をきっかけに、シニア人材の活躍を支える職場づくりを進めていくことが、企業の持続的な成長につながるはずです。
フォスターリンクでは、制度設計や見直しなど、専門家が伴走してしっかりと支援いたします。
また、制度設計だけでなく、人事データ管理、勤怠システム設定代行、給与計算アウトソーシングまで、人事労務運用を万全に行っていくためのソリューションを幅広く取り揃えています。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。
当社のサービスで解決できます!
- 制度設計支援:高齢者雇用に対応した就業規則・契約設計をサポート
- 人材管理クラウド:年齢・報酬・年金情報を一元管理
\ 詳しい内容はこちらからダウンロードできます /
7.参考文献
厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて
総務省 「労働力調査」 (2024年)
内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」(2024年)
日本年金機構ウェブサイト