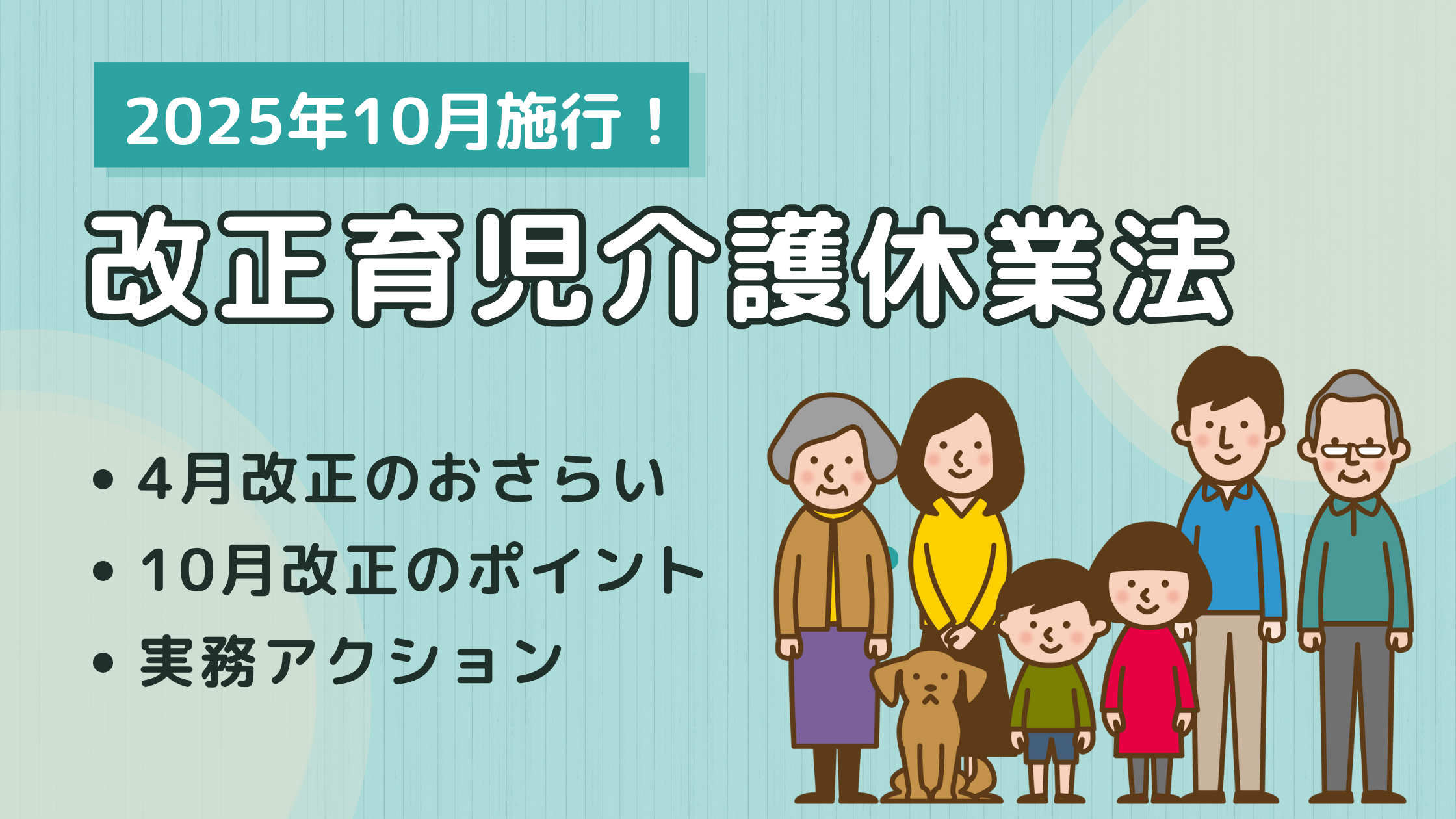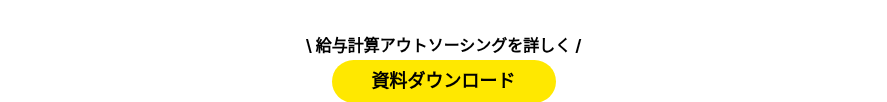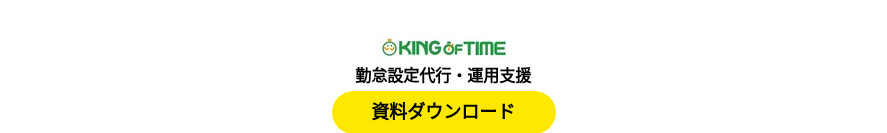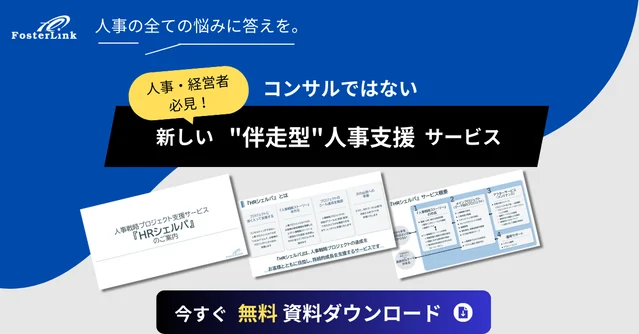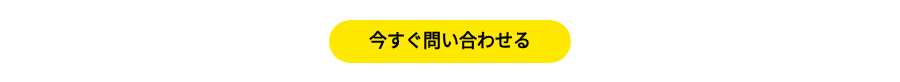2025年は、育児・介護休業法にとって転機の年と言えるでしょう。4月1日施行の第1段階に続き、10月1日にはさらなる改正が迫っています。企業にとっては、人材の定着促進や多様性経営の重要な契機でもあります。
本記事では、2025年4月改正を確認しながら、2025年10月改正の内容とポイント、実務担当者のアクションなどを整理します。
1.改正の概要
今回の改正法は二段階で施行され、まず2025年4月1日に第一段階が、続いて2025年10月1日に第二段階が施行されます。
この章では、以下のポイントを中心に概要と目的を整理します:
1. なぜ法改正が行われるのか~背景と目的
2. 4月施行の改正内容のダイジェスト
3. 10月施行(本記事の主眼)への流れ
1‑1. なぜ法改正が行われるのか?——背景と目的
背景には、日本が直面する少子高齢化と人口減少の問題、そして働き方の多様化への対応があります 。政府は、「育児・介護と仕事の両立が当たり前の社会」という目標を掲げ、その後押しとして2022年~2023年に育児・介護休業の取得率向上(特に男性)を目的とした改正がありました。
育児・介護休業は、、取得率、取得期間ともに男女間には大きな差があります。
取得率については、女性は8割で推移している一方で、男性は上層傾向にあるものの、令和5年時点で30.1%にとどまります。

引用:厚生労働省:令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について
取得期間についても、女性の約9割が6か月以上取得しているのに対して、男性は2週間未満が約4割、3か月未満が5割弱の取得であり、6か月以上の取得は1割に満たない状況です。

引用:厚生労働省:令和5年度育児休業取得率の調査結果公表、改正育児・介護休業法等の概要について
このような現状を受け、今回の法改正も、育児や介護を理由に仕事を辞める人を減らし、男女ともに柔軟に働ける環境を整備することが狙いとなっています。
1-2. 2025年4月施行の改正まとめ(ダイジェスト)
まずはスタートラインとなる、2025年4月1日施行の改正を振り返りましょう。
| NO | 改正項目 | 詳細内容 |
| 1 | 子の看護休暇(改称:子の看護等休暇) | ・対象年齢が「小学校就学前」から「小学3年生修了」まで延長 ・ 取得理由の拡充(「学級閉鎖」「入園・卒園式」の参加など) ・ 除外できる労働者の条件「継続雇用期間6か月未満」の撤廃 |
| 2 | 残業免除(所定外労働制限)の対象拡大 | これまで「3歳未満の子」に限定されていた範囲が、「小学校就学前の子」にまで広がりました |
| 3 | 短時間勤務の代替措置にテレワーク追加 | 育児短時間勤務が適用できない業務では、代替措置にテレワークが追加となりました |
| 4 | テレワークの努力義務化 | 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます |
| 5 | 育休取得状況の公表義務の拡大 |
男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」の公表が年一回必要な対象企業が「従業員1,000人超」から「300人超」にまで広がります |
| 6 | 介護休暇取得の要件緩和 | 除外できる労働者の条件「続雇用期間6か月未満」の撤廃 |
| 7 | 介護離職防止のための雇用環境整備 | 研修実施や窓口設置、事例の提供や利用促進に関する方針の周知など、介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするための措置を講じる |
| 8 | 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 | 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 |
| 9 | 介護のためのテレワーク導入 | 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます |
2.2025年10月改正の詳細
2025年10月1日施行の改正では、4月改正で導入された制度が土台となり、さらに企業に具体的な制度整備と運用を求める内容に踏み込みます。つまり企業が実際に制度を提供し、従業員個別への対応を徹底することが求められています。ポイントとなるのは以下の2点です。
▼3歳〜小学校就学前の子を持つ労働者に対して
• 柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け
• 個別周知・意向確認・配慮の義務付け
2-1. 柔軟な働き方を実現するための措置等
(1) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
|
対象 |
3歳から小学校就学前の子を育てる労働者 |
|
企業義務 |
下記の5施策のうち、2つ以上を選び提供し、従業員が選んで利用できる仕組みを構築すること 1. 始業・終業時間の変更(フレックス/時差出勤など) 2. テレワーク(月10日以上、時間単位での取得が原則) 3. 自社保育施設設置やベビーシッター手配&費用補助 4. 養育両立支援休暇(年10日以上・時間単位取得が原則) 5. 短時間勤務(例:1日6時間勤務制度) ※上記施策の中で既に企業で実施中のものがあれば、それカウントできます。 |
|
利用方法 |
従業員は事業主が講じた措置の中から1つ選択して利用可。 |
• フルタイム勤務を前提にしながら、働きやすさを提供
• テレワークや支援休暇は時間単位取得が原則
• 中小企業でも導入義務がある
• 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
|
周知時期 |
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 |
|
周知事項 |
① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 |
|
個別周知・意向確認の方法 |
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |
▼ポイント
• 対象期間:子が3歳になる1か月前までの1年間(概ね子が1歳11か月から2歳11か月まで)
• 対応内容:
o 提供している施策の内容と申出窓口の案内
o 所定外労働や深夜労働制限の制度概要も含めて説明
o 面談・書面・メール・FAX等、従業員に合った方法で提供
2-2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
|
意向聴取の時期 |
① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき |
|
聴取内容 |
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) |
| 意向聴取の方法 |
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか |
(2) 育児と仕事の両立に関する「意向聴取&配慮」
(1)で聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません
▼具体的な配慮の例
• 勤務時間帯、勤務地にかかる配置 ・両立支援制度等の利用期間等の見直し• 業務量の調整 ・労働条件の見直し 等
3.実務担当者のアクション項目
運用に向けて必要なアクションを整理します。実務担当者は、「何を・いつまでに・どう進めるか」を明確にしましょう。
制度設計だけでなく、労使協議や周知、運用プロセスの検討、勤怠、給与システム等への反映など、アクションは多岐にわたります。もれなく対応できるよう、早めに慎重に進めましょう。
3‑1. 提供施策の選定と、規程類の修正対応
• どの施策を導入するか
法律で定める以下の5施策から2つ以上を、自社の業務実態や従業員ニーズに応じて選択します
①始業・終業時間の変更(フレックスタイム/時差出勤)
②テレワーク(月10日以上、時間単位可)
③保育施設の設置運営(自社保育/ベビーシッター補助含む)
④養育両立支援休暇(年10日以上、時間単位取得可)
⑤短時間勤務制度(例:1日6時間制)
なお、選定に際しては、過半数代表または労働組合との意見聴取が必須です
• 影響を受ける規程類の洗い出し
作成や改定が必要な規程類を洗い出し、修正案を作成します。
厚生労働省が規定例や社内様式例を提供しているので、必要に応じて活用するとよいでしょう。
【参考】: 厚生労働省(育児・介護休業等に関する規則の規定例)
• 過半数代表者からの意見徴収と労使協定の締結
規程の修正内容についても、過半数代表または労働組合からの意見を聴取し、また必要に応じて労使協定の締結をします
• 労働基準監督署への提出
作成や修正した規程などを管轄の労働基準監督署へ届け出ます
3‑2. 社内体制構築と社内管理者研修
• 社内への周知
説明会の開催やガイドの作成、社内ポータルへの掲載などを通じて、従業員に周知します。対象者だけでなく、従業員がいつでも確認、利用できる形にしておくことが大切です。
• 管理者向け研修
制度概要、申請手続き、面談対応・記録方法、フォローのポイントなど、管理職向けに共有します。実際の制度運用には、管理職の現場での対応力が欠かせません。
• 社内FAQ・案内資料の整備
対象者に向けた分かりやすい資料を作成し、イントラやメールで周知。窓口・相談先も記載しておきます。
3‑3. システム対応
• 勤怠・申請管理システム対応
以下の項目をシステムに反映する設定が必要です:
- フレックスタイムの清算、時差出勤の打刻
- テレワークの日数・時間単位計上
- 養育両立支援休暇、短時間勤務の運用
• 人事・給与システムの反映
制度利用状況の記録、時間単位休暇の計算、賃金調整チェックが可能な設定・機能を整備します。
• アウトソーシングの活用
制度改定に自信がない場合は、給与計算のアウトソーシングや勤怠管理の設定代行などの利用がおすすめです。法令遵守にも対応でき、運用も委託できるメリットがあります
3‑4. 実際の運用(対象者への提供施策の周知と個別意向聴取)
• 周知の実施
対象従業員(3歳未満の子どもを持つ労働者)へ、施行日前または施行時から利用可能であることを周知します
• 個別意向聴取の実施
子どもが1歳11か月~2歳11か月の間に、
- 提供制度の説明
- 制度利用の意向確認
- 就業に関する希望(勤務時間帯・勤務地・支援制度)
について、個別面談/書面/メール等で実施し、記録を保存します。
3‑5. 配慮措置とフォロー対応
• 意向に基づく配慮
聴取内容に応じて勤務条件や業務配分、在宅環境など可能な範囲で配慮し、対応を記録します。
• 再確認・フォロー
状況変化に応じて意向や配慮内容を再確認し、必要に応じ見直します。
3‑6. 記録・モニタリング・運用見直し
• 記録保持
面談記録・意向聴取内容・配慮対応は、勤務記録と合わせて保存。行政調査や申立て時に備えます。
• 定期検証
年1回を目安に運用状況を確認し、制度設計・社内運用・システム対応を見直します。
4.注意点とリスク管理
2025年10月の改正では、細かな要件や実務対応の正確性が問われます。ここでは人事・労務担当者が特に注意すべき5つのポイントを、根拠とともにわかりやすく整理します。
4‑1. テレワーク・支援休暇は「時間単位取得」を原則とする
システムや就業規則において「時間単位取得を不可」としていると法令違反となる恐れがあります。
デイリー単位ではなく柔軟な時間単位設定(例:1時間単位)を整備しましょう。
4‑2. 「労使協定」は過半数代表との調整・意見聴取が必須
柔軟な働き方施策の導入にあたっては、就業規則改訂だけでなく事前に過半数労働組合または代表者との意見聴取が必要です。
あくまで「意見を聴く」方式で、必ずしも同意は求められませんが、「いつ・誰に」「どのような意見を聴取したか」は記録しておくことが重要です。
4‑3. 個別意向聴取は“形式的ではなく実効性重視”で記録を徹底
「制度の周知・意向確認」は書面や面談、メール等により個別に実施・記録する必要があり、記録の保存義務が伴います。
「まだ決められない」という回答も意向として記録対象となります。形式的な対応にならないように注意が必要です。
また、「ふんわり案内」ではなく、制度利用の可否・希望日時などを具体的に聴取し、書面や記録が残るようにします。
4‑4. 就業規則・協定・運用の整合性を必ずチェック
制度内容、申請フロー、対象者・取得条件などは、就業規則・協定・実際の運用方法が一貫しているかをしっかり確認することが重要です。
5.システム導入&アウトソーシング活用提案
10月改正への対応を確実にしつつ、人事労務業務の効率化も図るため、以下のツール・サービスの導入を検討しましょう。
5‑1. 勤怠管理・打刻システム:フレックス・時短・テレワークに対応
- 求められる機能:
- フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークを正確に記録・管理できる
- モバイル/GPS打刻、PCログ打刻、複数打刻に対応し、柔軟な勤務形態にも対応可能
5‑2. 人事管理システム:意向管理・申請・面談記録機能
- 必要なポイント:
- 柔軟な働き方選択肢に対する申請・意向聴取・面談記録を一元管理
- リマインダーや履歴検索が可能で、個別フォローも漏れなく実施できるシステム設計に
- 導入メリット:
- 法定義務に基づく記録管理が簡易化され、報告・監査に迅速対応可
- 従業員ニーズに応じた制度利用状況の把握・フォローアップを自動化できる
5‑3. 給与計算アウトソーシング
- 期待する機能:
- 時短勤務・育児支援休暇・テレワークなどの賃金調整に関するテンプレート搭載
- 法改正に応じたアップデート、ミス防止チェック機能
- 選定時のポイント:
- 委託できる業務範囲、スケジュール感、役割分担が自社の要件とマッチしているか
- セキュリティレベルは十分か
給与計算代行については、こちらの記事も、ぜひ参考にしてください
6.まとめ|早めの対応、適切な支援でトラブル回避
スムーズな運用を実現するためだけでなく、労務トラブルやコンプライアンス違反を防ぐためにも、運用に向けた準備を早めに、万全に行うことが不可欠です。
しかし、法改正対応には、これまで述べてきたように、規程の見直しだけでなく、周知や業務プロセス、労務システムの変更など、多岐にわたるアクションが必要になります。
フォスターリンクでは、制度設計から人事データ管理、勤怠システム設定代行、給与計算アウトソーシングまで、人事労務のお悩み事を解決するソリューションを幅広く取り揃えています。
お悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください
▼「人事制度設計支援」のくわしい内容については、こちらから無料ダウンロードできます。
▼支援実績20年以上!まずはフォスターリンクへお気軽にお問合せください。