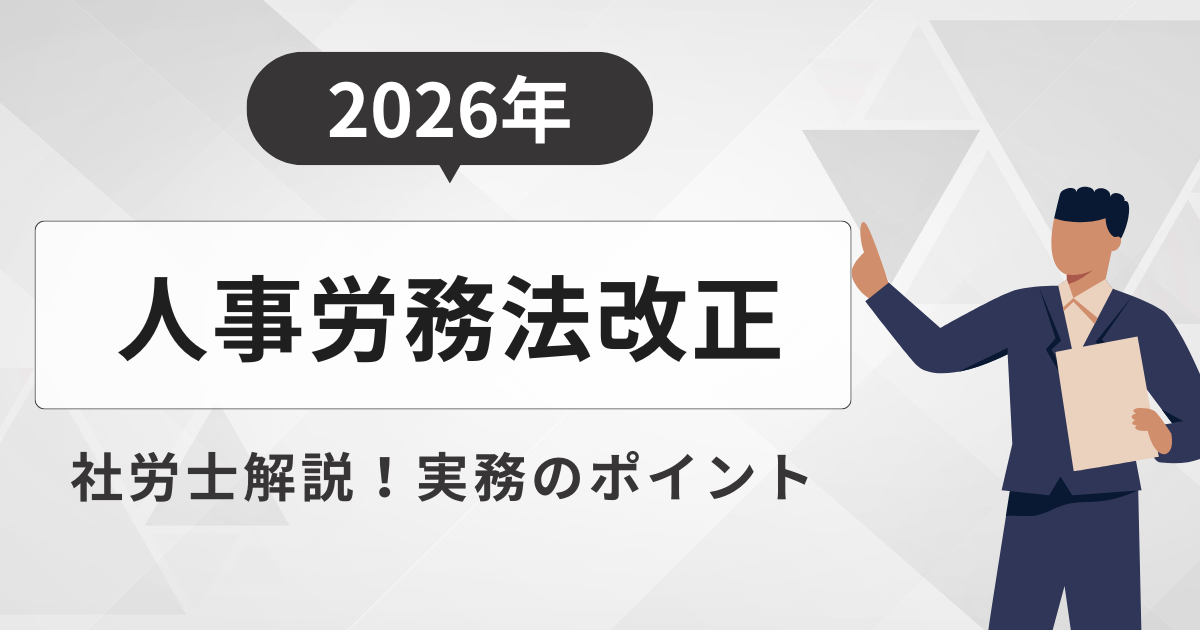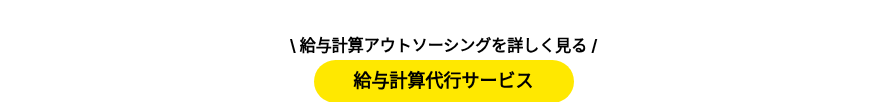2026年は、人事・労務分野において多岐にわたる法改正が予定されており、企業の実務対応に大きな影響を与える年になります。
本稿では、社労士の観点から2026年に施行・検討される主要な人事労務関連法改正を整理し、企業が準備すべき実務対応を解説します。
1.2026年改正が確定している人事労務関連法
1-1.年金制度改正
在職老齢年金の支給停止基準額が「月50万円 → 62万円(2024年度価格)」に引き上げられます。
施行は2026年4月1日。高齢社員が働きながら年金を受け取りやすくなります。
|
【実務のポイント】 対象となる従業員への情報周知、人件費のシミュレーションが必要となります。 65歳以降の短時間再雇用制度、賃金テーブルなどがある企業は、設計と規程の見直しも行います。 在職老齢年金制度については複雑なため、改正前後での社会保険料・年金受給の説明資料も用意してきましょう。
|
1-2. 女性活躍推進法改正
101人以上の企業に対して
① 男女間賃金差異
② 女性管理職比率
の公表が義務化されます。
施行は2026年4月1日。また同法の有効期限は2036年3月31日まで延長されています。
|
【実務のポイント】 定義が曖昧な場合は、非正規雇用の社員なども含めた管理職の定義を定めておきます。 また、開示するKPIについて、算出基準やデータ抽出の流れを確認しておきましょう。
|
1-3.ハラスメント関連の改正
カスタマーハラスメント対策、就活セクハラ防止措置が義務化されます。
公布は2025年6月11日。
1年6か月以内に政令で定める日(=遅くとも2026年末頃までに)に施行予定です。
|
【実務のポイント】 その後、社内外への掲示物・web掲示の整備、相談窓口の拡充なども重要です。 また、求人から採用、内定者対応までを対象とした就活セクハラ対策の手順書を作成しておきましょう。
|
1-4.労働安全衛生法・作業環境測定法の段階施行
2025年に成立した改正労働安全衛生法・作業環境測定法は、2026年を起点に段階施行されます。
主な骨子と期日は以下の通りです。
▪︎個人事業者(フリーランス等)にも安全衛生の枠組みを拡充
注文者の措置義務や本人の教育受講等
一部は2026年1月1日、同年4月1日、2027年1月1日、同年4月1日へ段階施行。
▪︎化学物質対策の強化
危険有害性情報通知違反への罰則、営業秘密の代替化学名の限定容認、個人ばく露測定の位置付け明確化等
一部は2026年10月1日に施行。
▪︎機械等による労働災害の防止の促進
民間の登録機関の検査範囲を拡大、検査基準への遵守義務
2026年1月1日、4月1日に施行。
|
【実務のポイント】 施行期日がそれぞれ異なるため、対象となる施行期日を整理し、年次計画に組み込むことが重要です。 個人事業者への拡充については、契約時に安全衛生配慮条項の整備や教育受講体制の確認が必要となります。 化学物質対策の強化については、代替化学名の判断手順や測定体制の整備、専門機関との連携を行い、機械等による労働災害の防止の促進は、検査計画を立てて遵守していく体制作りが大切です。
|
1-5.子ども・子育て支援金の創設
子ども・子育て支援金とは、少子化対策を目的に新たに創設された制度で、医療保険料に上乗せして徴収し、その財源を子育て関連施策に充てる仕組みです。

引用:こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について(令和7年3月)
こども家庭庁の試算によると、一人あたりの納付額は全制度の平均で250円〜450円ほどとなる見込みですが、加入者の年収や加入保険によっても異なります。
|
【実務のポイント】 新設される制度のため、従業員や経営層への説明・周知が必要となります。 また、給与計算システムの更新も忘れずに行いましょう。 増加する企業コストを試算し、予算計画に盛り込むことも重要です。
|
2.2026年に想定される労基法改正(審議中の論点)
厚労省の労働基準関係法制研究会報告書を受け、早ければ2026年改正を目指す論点が労政審で議論中となっています。
主に議論されている論点は以下の5点です。
・労働時間規制の変更
・休日・休暇制度の見直し
・副業の際の割増賃金の通算見直し
・勤務間インターバルの義務化
・有給取得時の賃金算定の変更
今回の改正ポイントは多岐に渡る予定です。
今のうちから就業規則、勤怠システム、研修、運用フローなどを確認し、内部体制を整理しておくことが、法改正後のスムーズな対応とコンプライアンス確保につながります。
3.中期的に押さえておくべき改正予定
2026年以降も、既に多くの人事労務関連法の改正が議論されています。
2025年9月時点での最新情報を元にまとめてありますので、事前にチェックしておきましょう。
3-1.短時間労働者の社会保険適用拡大
現時点では、51人以上の企業等で働き、以下4つの条件全てに当てはまる場合、社会保険加入の対象者となります。
| ①週の所定労働時間が20時間以上 |
| ②賃金が月8.8万円以上 |
| ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある |
| ④学生ではない |
今後、この企業規模要件と、②の賃金要件の見直しが予定されています。
以下に詳しく説明します。
(1)企業規模要件の段階的縮小・撤廃
2027年10月1日から2035年10月1日までの間に、段階的に縮小・撤廃されます。

引用:厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
この改正により、2035年10月以降は、従業員が1人でも在籍し、上述した社会保険加入条件に当てはまる場合は、加入の義務が発生することになります。
(2)賃金要件の3年以内の撤廃
これまで「106万円の壁」(8.8万/月)と言われて賃金要件が、3年以内に撤廃されることが決まりました。
撤廃の時期は、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます。
3-2. 雇用保険制度の適用拡大
現在、雇用保険の加入要件は週20時間以上の勤務者ですが、2028年10月1日より、週10時間以上の勤務者も加入対象となります。
3-3.障害者法定雇用率の引き上げ
障害者法定雇用率が、2026年7月から2.7%に引き上げられます。(国および地方公共団体等は3.0%、教育委員会は2.9%)
これにより、従業員数が37.5名以上の企業に障害者の雇用義務が発生します。
3-4.標準報酬上限の段階的引き上げ
厚生年金の保険料や年金額の計算に使用する標準報酬の上限が段階的に引き上げられます。
具体的な引き上げのスケジュールは、以下の通りです。
| 引き上げ時期 | 標準報酬上限額 |
| 2027年9月 | 68万円(現行65万円) |
| 2028年9月 | 71万円 |
| 2029年9月 | 75万円 |
4. よくある誤解と注意点

2026年の人事関連法改正において陥りがちな誤解と注意点をまとめました。
4-1.ストレスチェック義務の拡大
ストレスチェックは、2026年4月から全社で義務となるわけではありません。
50人未満の事業場への義務化は、公布後3年以内に定める日となります。(=最長2028年5月まで)
まずは体制整備を先行しつつ、施行日の公示を確認していくようにしましょう。
4-2.子ども・子育て支援金の負担
子ども・子育て支援金は従業員が全額負担するものではありません。
健康保険・厚生年金加入者の保険料に含まれ、会社と従業員が折半で負担します。
5.まとめ | 法改正の負担を軽減するには
法改正に対応するには、システム修正や規程の見直しが必要となり、担当者の負担は年々増えています。
特に給与計算は、社会保険料の変更や新制度の導入時にミスが生じやすい領域です。
弊社の給与計算代行サービスなら、専門家が常に最新法改正を踏まえた正確な処理を行い、安心して本業に集中いただけます。
ぜひお気軽にご相談ください。
\ フォスターリンクの給与計算アウトソーシングサービス 資料ダウンロードはこちら /
6.参考文献
・こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について(令和7年3月)
・厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について