「従業員に安心して長く働いてもらいたい」「魅力ある福利厚生を整えて人材を確保したい」
そんな思いを抱える企業経営者・人事担当者にとって、近年注目されているのが企業型確定拠出年金(企業型DC)です。
この記事では、企業型確定拠出年金の仕組みやメリット・デメリット、導入のポイントまで、社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。
1.確定拠出年金とは?
まず、確定拠出年金とは、企業または加入者が拠出した掛金をもとに、加入者自身が運用し、老後資金を形成していく年金制度です。
大きく分けて以下の2種類があります。
- 企業型確定拠出年金(企業型DC):企業が掛金を拠出する制度
- 個人型確定拠出年金(iDeCo):個人が自ら加入し、掛金を拠出する制度
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の違い
上述した2種類の確定拠出年金には、それぞれ下記のような違いがあります。 個人が任意で加入する年金制度である個人型確定拠出年金(iDeCo)とは異なり、企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために導入する年金制度です。老後の資産形成を企業が支援する福利厚生の一つとなります。
個人が任意で加入する年金制度である個人型確定拠出年金(iDeCo)とは異なり、企業型確定拠出年金は、企業が従業員のために導入する年金制度です。老後の資産形成を企業が支援する福利厚生の一つとなります。
本記事では、特に企業が導入する企業型確定拠出年金に焦点を当てて解説します。
2.企業型確定拠出年金の基本的な仕組み

企業型確定拠出年金では、企業があらかじめ定めた掛金を毎月従業員の専用口座に拠出(積み立て)します。
従業員は、その掛金を用いて自ら運用商品(投資信託や定期預金など)を選び、老後の資産形成を行っていきます。
将来の受取額は運用成績によって変動し、運用は従業員本人の責任となります。
企業にとっては掛金額が確定しているため、コスト管理がしやすい制度です。
企業型確定拠出年金には、従業員が自動的に加入する場合と、企業型確定拠出年金に加入できるかどうかを選択できる場合の2つがあります。後者の場合、従業員は、給与または賞与の一部について、掛金として拠出するか、給与として受け取るかを選択することができます。
後述する社会保険料の削減効果とも相まって、近年では中小企業を中心に導入が増加している傾向が見られます。
3.確定拠出年金と確定給付年金の違い
確定拠出年金と混同されやすい制度に、確定給付企業年金があります。
どちらも企業が従業員の老後資金を準備するための制度ですが、仕組みやリスクの負担先が大きく異なります。
以下に、ポイントを押さえて説明します。
3-1.確定しているものの違い
確定拠出年金が確定しているのは、毎月の掛金額(=拠出額)です。
上述した通り、将来いくらもらえるかは従業員自身の運用次第となります。
一方で、確定給付年金では、将来の受取額(=給付額)があらかじめ決まっている制度です。
運用に関しては企業もしくは運用機関が責任を負い、約束した金額を支払うのが大きく異なる点です。
3-2.将来の受取額
確定拠出年金は従業員自身が運用の指図を行うため、運用次第で将来の受取額が増えることもあれば減ることもあります。
一方で、確定給付年金はあらかじめ受取額が決まっています。
そのため、従業員にとっては後者のほうが老後設計しやすい制度と言えるでしょう。
3-3.企業側の負担と管理
確定拠出年金は、制度がスタートしたら基本的には毎月掛金を拠出すれば良いだけとなります。
掛金についても決まっているため、コストが見通しやすく将来の負担が増えずらい特徴があります。
それに対して、確定給付年金は将来の支払い額が決まっているので、運用がうまくいかなかった場合、企業が補填しなければならなくなります。
そのため、管理が複雑になりやすいという点が挙げられます。
4.企業型確定拠出年金を導入するメリット
企業型確定拠出年金を導入することは、企業にとって人材定着・財務安定・社会的信頼の向上など、さまざまなメリットがあります。以下では、社会保険労務士の視点から実務的なメリットを解説します。
4-1.税制面・社会保険料面での優遇
企業型確定拠出年金の事業主掛金は、全額損金として計上することができます。
損金を計上すると、利益分が減るため、法人税の支払額が少なくなります。これが企業にとっての節税効果となります。
また、事業主掛金は所得扱いとならないため、社会保険料の対象にもなりません。
社会保険料は、従業員と企業が半分ずつ負担する労使折半となりますが、その対象外となります。
よって、社会保険料の折半額も減り、削減につながっていきます。
(※保険料額が変更されるタイミングについては、各保険料毎に異なります。)
.png?width=711&height=400&name=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(2).png)
4-2.従業員の定着率向上・モチベーションアップ
制度を導入することによって、従業員に老後に向けてという長期的な安心感を提供できます。
特に若手や中堅層にメリットの多い制度のため、次世代リーダーとなり得る人材の離職防止に役立ちます。
また、加入者が勤続3年未満で退職した場合、「事業主返還」を適用させる年金規約の設定も可能です。
こうした制度設計によって、早期の離職リスクを低減していくこともできます。
4-3.採用競争力の向上
企業型確定拠出年金を導入することは、求職者にとっての魅力的な福利厚生制度となり、他社との差別化につながります。
特に近年では、若年層から中堅層まで将来の資産形成や老後の不安解消を重視する傾向が高まっています。
こうしたことからも、企業イメージの向上と求職者の応募意欲の増加につながると言えるでしょう。
▼企業型DCの無料ガイドブックは、こちらからダウンロードできます
5.企業型確定拠出年金導入時の注意点
企業型確定拠出年金を導入する際には、制度の設計や運用面において複数の注意点があります。
以下に、企業側が把握しておくべき主な注意点を詳しく解説します。
5-1.労使合意と就業規則変更の手続き
導入時には労使間で合意を得て、就業規則の変更手続き(常時雇用の労働者が10人以上の場合)が必要です。
特に選択制確定拠出年金で給与構造を変える場合は、労働条件の不利益変更と見なされないように注意しましょう。
また、社会保険料や給付に関しても、給与の減額に伴う影響に注意が必要です。
5-2.掛金額と拠出ルールの設計
拠出額には、以下のように月額の上限が定められています。
| 確定拠出年金のみの場合 | 55,000円まで |
| 確定拠出年金と確定給付年金を併用している場合 | 55,000円から確定給付型企業年金等の掛金相当額を差し引いた金額 |
| マッチング拠出の場合 | 会社掛金と同額まで、かつ合算で55,000円まで |
過大な掛金設定は企業負担が重くなり、経営に影響を及ぼす可能性があります。
一方で、少なすぎる掛金では、従業員にとってのメリットが見えにくく、制度の魅力が薄れます。
適切な水準を見極め、経営体力や人事制度と整合性を取る必要があります。
5-3.投資教育の実施
確定拠出年金では、運用成果は従業員本人の責任になります。
しかし、投資教育の提供は企業の義務とされており、投資リテラシーの低い従業員に対する適切なサポートが求められます。
最低でも年1回の継続した投資教育の実施が望ましいとされています。
このように、制度設計から運用まで、確定拠出年金の導入には専門的な知識が必要となります。
状況によっては、経験・知識が豊富な外部の専門家に頼ることも重要です。
フォスターリンクの「HRシェルパ」なら、経験豊富な専門家が貴社の確定拠出年金の導入もしっかり伴走して支援します。
6.企業型確定拠出年金のよくある誤解
企業型確定拠出年金は、制度が複雑であるため、導入を検討する企業や加入する従業員の間で誤解されやすい点が多々あります。
以下によくある誤解とその正しい理解を整理して解説します。
退職金と併用できないのでは?
企業型DCは他の退職給付制度(確定給付企業年金、退職一時金など)と併用可能です。
実際、多くの企業が既存の制度と並行して導入しています。
近年では、リスク分散の観点から確定給付型と確定拠出型のハイブリッド型制度を選ぶ企業も多く、従来の退職金制度を補完・強化する制度として企業型確定拠出年金が活用されています。
中小企業では導入できないのでは?
中小企業でも導入できます。
実際に企業年金連合会のアンケート調査を見ても、確定拠出年金加入済企業の約39%が300名以下の企業であるというデータもあります。(引用:企業年金連合会 確定拠出年金実態調査結果[2022年])
また、2020年10月からは従業員が300人以下の企業に対して、中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)などの制度も拡充しています。
このように、手続きが簡素化されている制度や従業員の状況に合わせた制度設計がしやすいサービスも出てきていることから、中小企業でも始めやすい制度となっています。
運用リスクが怖いので導入できない…
企業型確定拠出年金の運用リスクは従業員が負います。
また、商品によっては元本保証型のものもありますので、従業員の意向次第でリスクを抑えた運用も可能です。
企業型DCでは、従業員が自ら運用商品(投資信託や定期預金など)を選択します。
そのため、元本保証型を選べばリスクを抑えた運用も可能です。
むしろ、老後資金の自助努力を支援する制度として企業型確定拠出年金を活用することは、従業員の長期的な安心にもつながると言えるでしょう。
7.まとめ|確定拠出年金は企業の武器になる
少子高齢化が進み、採用難や人材の定着が経営課題となる今、企業型確定拠出年金は単なる福利厚生にとどまらず、企業の信頼性や魅力を高める“戦略的な制度”として注目されています。
従業員の将来に寄り添う姿勢は、エンゲージメントの向上にも直結します。
中長期的な人材投資として、いまこそ制度導入を真剣に検討してみてはいかがでしょうか。
フォスターリンクの「HRシェルパ」なら、経験豊富な専門家が貴社の確定拠出年金の導入もしっかり伴走して支援します。
▼「HRシェルパ」のくわしい内容については、こちらから無料ダウンロードできます。
参考資料
- 企業年金連合会 確定拠出年金実態調査結果[2022年]

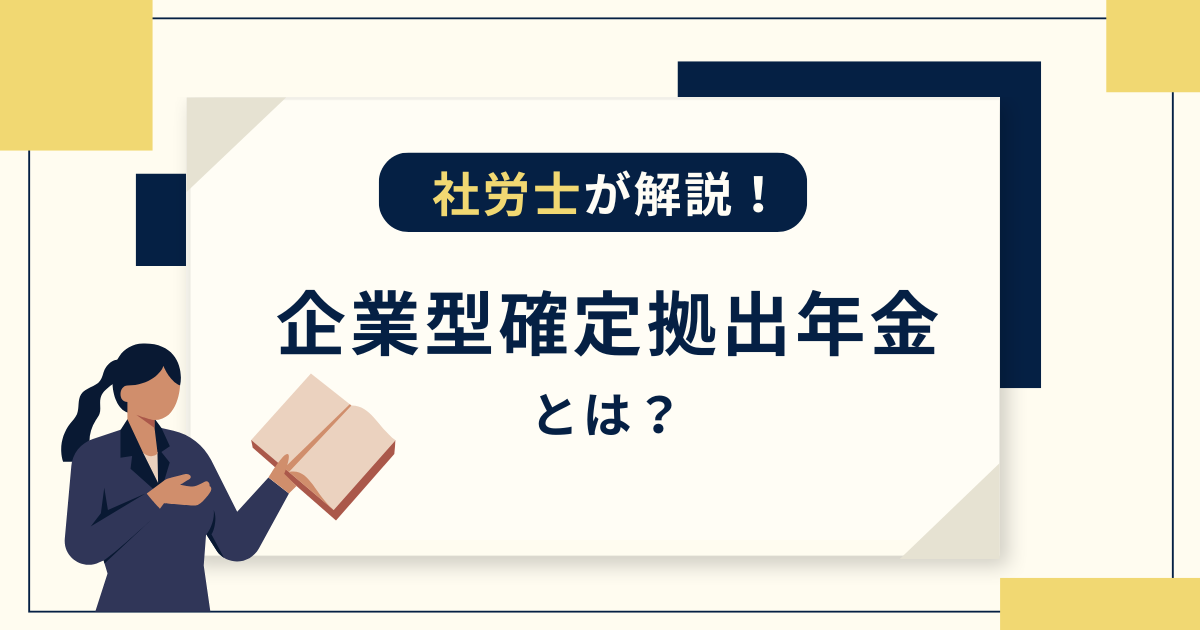
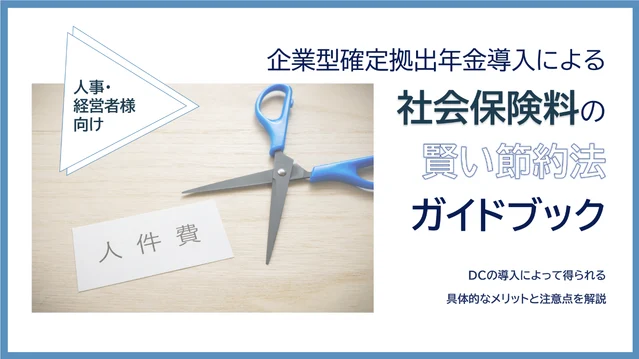
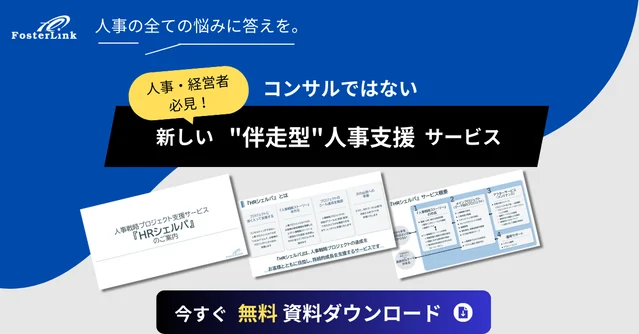
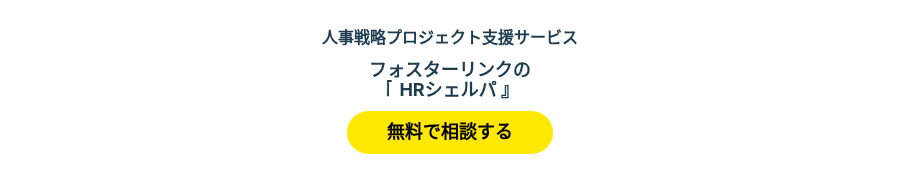
.png?width=624&height=427&name=%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%9E%8B%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%20(5).png)

