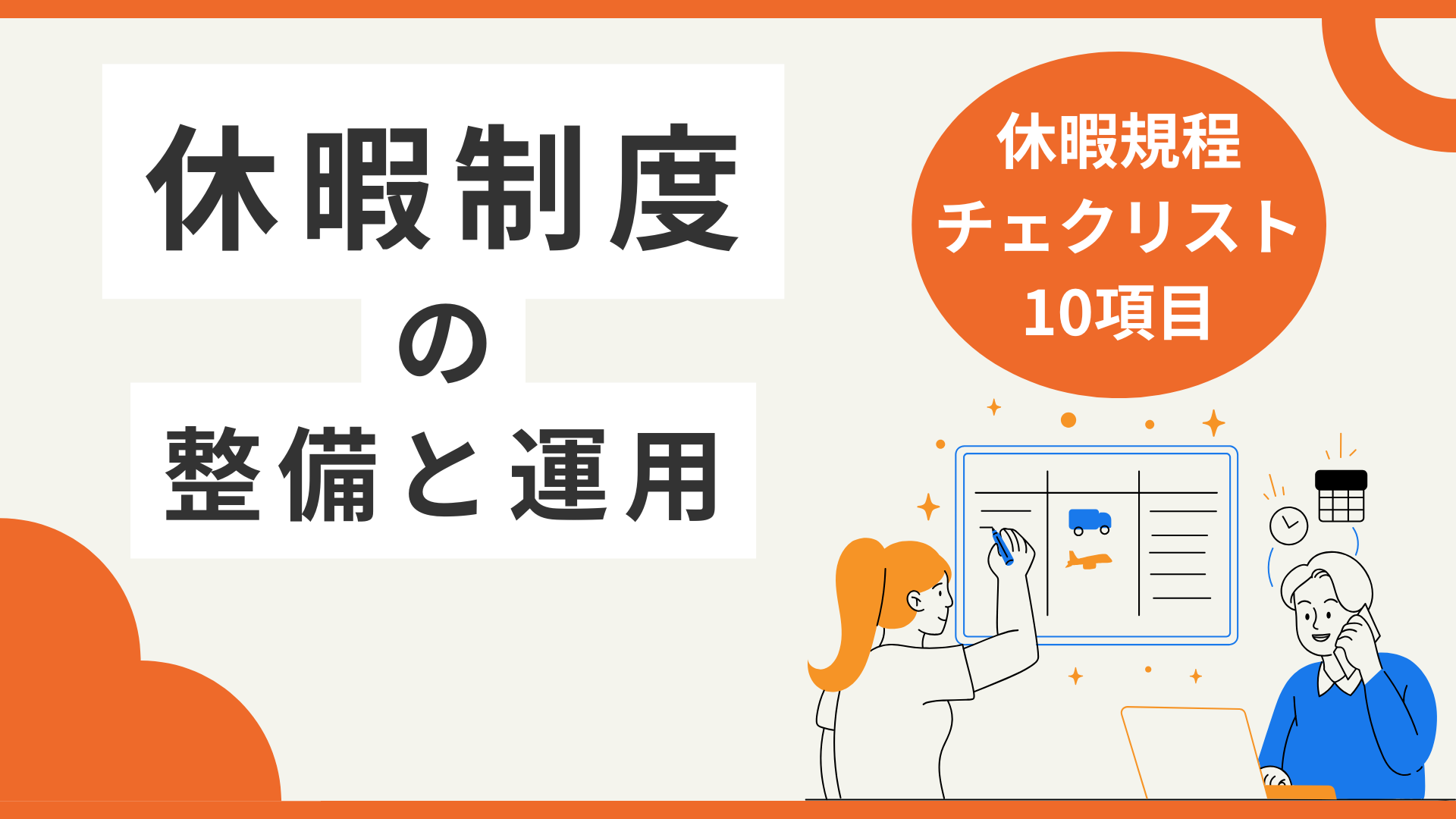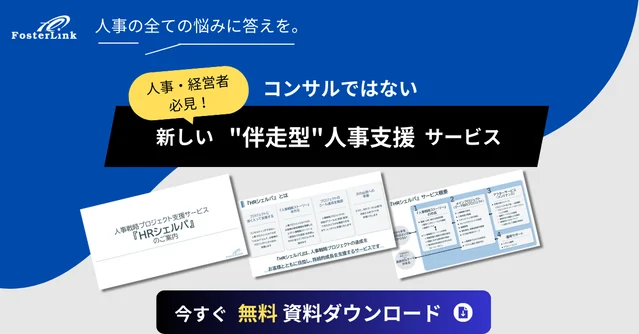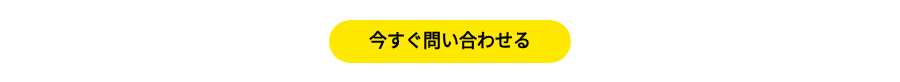働き方改革の推進や男性育休制度の義務化、人的資本経営への注目など、企業を取り巻く労務管理の環境はここ数年で大きく変化しています。その中でも「休暇制度」は、従業員のエンゲージメントや健康経営に直結する重要な制度のひとつです。
しかし、多様化・複雑化する制度に対し、「就業規則が現状に合っていない」「休暇の種類が多すぎて管理が煩雑になっている」といった課題を抱えている企業も少なくありません。
特に有給休暇や育児・介護休業などの法定休暇に加え、慶弔休暇やボランティア休暇、リフレッシュ休暇、ライフサポート休暇、サバディカル休暇といった任意の特別休暇まで含めると、その整理と運用は一層難しくなります。
本記事では、休暇制度の運用を見直す際に役立つ「休暇規程のチェックリスト10項目」と、留意すべきポイント、ありがちなトラブルとその対処法をご紹介します。
規程と実務のズレを解消し、スムーズな制度運用を目指すためのヒントとして、ぜひご活用ください。
休暇とは?基本の定義と種類
まずは、そもそも「休暇」とは何かを整理しておきましょう。
休暇の定義と休日との違い
「休暇」とは、もともと労働義務がある所定労働日に対して、「その日の労働義務を会社が免除する日」を意味します。英語では “vacation” とも訳されます。これに対し、「休日」はそもそも労働義務が発生しない日(土日祝などを利用して、企業が事前に休みとして定めている日 )を指します
必ず与えなければならない「法定休暇」と任意で設定する「法定外休暇」
1. 法定休暇(法で定められた休暇)
取得要件を満たす対象者に、法律によって付与が義務付けられている休暇には、以下が含まれます
• 年次有給休暇
• 生理休暇
• 妊娠休暇・通院休暇
• 産前産後休業
• 子の看護等休暇
• 介護休暇
• 出生時育児休業
• 育児休業
• 介護休業
• 裁判員休暇
法定休暇は、企業が付与義務を負う「権利」でもあり、管理漏れや取得妨害があった場合、法的リスクにもつながります。ただし、有給休暇以外の休暇は「有給」・「無給」を企業判断で決定することが可能です。
2. 法定外休暇(任意休暇)
企業が独自に設定する休暇です。代表例として、慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などが挙げられます。こちらも 就業規則で内容や有給・無給を定める必要があり、福利厚生の一環として従業員の満足度や定着率向上に寄与します。
休暇取得の目的
休暇は従業員にとって「心身のリフレッシュ」「生活と仕事の両立支援」の手段です。
企業にとっても、「労基法順守」「離職率低下」「生産性改善」の観点から重要な検討ポイントとなっています。
規程にズレはない?休暇制度見直しチェックリスト10項目
休暇制度の見直しに取り組む際、まず確認すべきは「社内規程が現行の法令や運用実態と合っているかどうか」です。規程が古いまま放置されていると、従業員の誤解や運用ミスにつながります。
ここでは、労務担当者が休暇規程の見直し時にチェックすべき10のポイントを解説します。
1. 年次有給休暇の「年5日取得義務」に対応しているか
2019年の労働基準法改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年間5日の取得が義務付けられました。これに違反すると企業に罰則が科される可能性があります。規程上、年休の取得義務や、計画的付与制度の導入有無などが明文化されているかを確認しましょう。
参考:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501911.pdf
安易に企業任意の特別休暇の数を増やすと、有給休暇の5日取得義務を満たせなくなるリスクがあります。企業の実情に合わせた、休暇の数や取得順などのルール・運用を検討していく必要があります。
2. 時間単位年休の制度が明記されているか
時間単位で有給休暇を取得できる制度(時間単位年休)を導入している場合、対象者、取得可能な上限(年5日以内)、取得単位(1時間単位など)を明記しておく必要があります。導入していない場合は、その旨も明確にしておくとよいでしょう。
3. 産前産後・育児休業の条件と手続きが明文化されているか
産前産後休業や育児休業は法定の制度ですが、申請方法や提出書類、取得可能期間、職場復帰後の対応(時短勤務など)まで、社内の流れを具体的に記載することで、従業員の安心感と制度の利用促進につながります。
4. 産後パパ育休(出生時育児休業)の運用が整理されているか
2022年に新設された「出生時育児休業(いわゆる“パパ育休”)」は、従来の育児休業とは別枠で取得できる制度です。導入後も運用が曖昧なケースが多く、社内規程で取得の条件・申請手続き・分割取得のルールなどを定めておくことが重要です。
また、2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されています。そういった意味でもきちんと運用を整備しておくことが重要と言えます。
5. 介護・看護休暇の制度が整備されているか
要介護状態の家族がいる従業員向けの「介護休暇」、また小学校3年生修了まで の子どもを養育する従業員向けの「子の看護休暇」も、法定で認められている休暇制度です。これらが対象者・取得日数・取得単位(半日または時間単位)など明記されているか確認しましょう。
※2025年4月1日施行で育児介護休業法の改正がありました。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf?8991
6. 特別休暇(慶弔・夏季休暇 等)の種類と運用ルールが明確か
特別休暇は法定ではありませんが、多くの企業が導入しています。付与日数・対象者・取得期限などを明文化しておくことで、恣意的な運用を防げます。
7. 非正規社員(パート・アルバイト等)の取り扱いが規定されているか
正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規社員にも法定休暇は適用されます。特に有給休暇や育児・介護休業に関しては、契約内容や所定労働日数に応じた取り扱いを明示しておく必要があります。
8. 休職中の休暇付与・復職時の取り扱いが明確か
正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規社員にも法定休暇は適用されます。特に有給休暇や育児・介護休業に関しては、契約内容や所定労働日数に応じた取り扱いを明示しておく必要があります。
9. 休暇申請と承認のフローが整備されているか
休暇取得に関する管理は、制度を運用するにあたってとても重要なポイントです。 「申請→承認→記録」の流れが明文化されていることが望ましいです。
10. 実態と規程に乖離がないか定期的にチェックしているか
社内規程と実際の運用が乖離していると、トラブルの原因になります。制度を新設・変更した場合には必ず規程に反映させること、最低でも年1回の定期的な見直しをルール化しておくことが重要です。
規程を整備しても油断禁物?休暇制度運用で起きがちなトラブルと対応策
休暇規程をしっかり整備しても、実際の運用段階でトラブルが発生するケースは少なくありません。制度の内容や申請ルールが従業員に浸透していなかったり、担当者による対応のばらつきがあったりすると、労使間の信頼関係に影響を及ぼすこともあります。
この章では、休暇制度の運用で起こりがちな代表的なトラブルとその対応策について解説します。
トラブル① 有給休暇の申請が集中し、業務に支障が出た
よくあるケース:
年度末や繁忙期に、複数の従業員が一斉に年次有給休暇を申請し、現場が回らなくなるという事態は多くの職場で見られます。
対応策:
・計画的付与制度を導入する
・職場単位での「事前申請ルール」を明文化する
・業務量や人員配置に応じた「取得推奨時期」を周知する
年5日の取得義務を確実に果たしつつ、業務に支障が出ないようにバランスをとる運用が求められます。
トラブル② 法改正後の制度が現場で正しく理解されていない
よくあるケース:
出生時育児休業(いわゆるパパ育休)など、新たに制度が創設されたものの、従業員も管理者もその内容をよく知らず、申請対応に混乱が生じる。
対応策:
・制度改正時には、社内向けの案内資料や研修をセットで実施する
・制度ごとの「簡易ガイド」や「Q&A資料」を作成し、全従業員に配布
・特に管理職層には、申請があった際の流れや対応方法を事前に周知しておく
情報の整理と伝達は、制度浸透の要です。就業規則を変えるだけではなく、「使われる制度」にするための工夫が欠かせません。
トラブル③ 特別休暇の運用が属人化して不公平感が生まれた
よくあるケース:
同じ理由で休暇を申請したのに、部署ごとに対応が異なることで、「あの人は休めたのに、自分はダメと言われた」と不満が出る。
対応策:
・特別休暇の対象事由や取得条件を、できるだけ具体的に規程に記載
・運用ルールをマニュアル化し、管理者に共通認識を持たせる
・従業員からの申請に対する対応履歴を記録として残す
特別休暇のような任意制度は、運用の公平性を確保しないと不信感につながります。明文化と記録の徹底がカギです。
トラブル④ 担当者変更時に休暇データの引き継ぎが不十分だった
よくあるケース:
人事異動などで休暇管理担当者が交代した際、記録や手順の引き継ぎが不完全で、休暇残日数に誤りが発生。
対応策:
・休暇管理表や申請記録を一元管理(Excelまたはシステム)
・「運用マニュアル」を整備し、担当者ごとの属人的な処理を防ぐ
・定期的に第三者チェックや棚卸を行い、情報の正確性を保つ
休暇制度の信頼性は、情報の正確性にかかっています。特に有休や育休は、日数や取得履歴の整合性が求められるため、データの整備と運用ルールの標準化が不可欠です。
制度そのものを整備することは出発点に過ぎません。実際に「安心して使える」「管理しやすい」制度にするためには、こうした運用上の落とし穴をふまえた対応が求められます。
次章では、制度設計・運用の課題を外部の専門家と連携して乗り越える方法について解説します。
社内だけで抱え込まない!制度整備・運用に外部の力を活用する方法
休暇制度の見直しや運用改善は、人事労務担当者にとって重要な業務である一方、社内だけで完結させるには限界があります。
法改正への対応、制度設計、トラブル時の対応方針など、判断に迷う場面も多く、「他社はどうしているのか?」「この解釈で合っているのか?」といった悩みを抱えたまま進めている企業も少なくありません。
こうした状況を乗り越えるためには、必要に応じて外部の専門家の知見を取り入れることが有効です。ここでは、制度整備や運用において外部リソースを活用する際のポイントをご紹介します。
社会保険労務士(社労士)のサポートを活用する
休暇制度の見直しにおいて、最も頼りになる存在が社会保険労務士(社労士)です。社労士は、労働関係法令や労務トラブルに精通しており、以下のようなシーンで力を発揮します。
• 法改正への対応アドバイス(例:育児・介護休業法、働き方改革関連法など)
• 就業規則・休暇規程の見直し、条文化の支援
• 特別休暇の設計や他社事例の提供
• 育児・介護休業の個別ケースへの助言
特に近年は、法令の複雑化や従業員のニーズ多様化により、一般的なテンプレートでは対応しきれない場面も増えています。自社の業種・規模・組織構造に合わせたオーダーメイドの支援が受けられるのは、社労士ならではの強みです。
人事労務コンサルタントやサービス会社による実務支援も
最近では、社労士以外にも、人事労務に特化したコンサルティング会社やアウトソーシング企業が、休暇制度に関する支援サービスを提供しています。以下のような活用法があります:
• 管理テンプレートの導入・カスタマイズ支援
• 制度運用マニュアルの作成
• 社内説明資料や研修コンテンツの制作
• 勤怠管理システムとの連携サポート
こうした支援は「自社で制度を運用していく力を育てたいが、スタートアップ時には伴走してほしい」といったニーズに合致します。制度を整えるだけでなく、「従業員に伝わる仕組み」に落とし込む点でも力を発揮します。
\ 貴社の人事制度構築から運用支援までサポート。資料ダウンロードはこちらから /
外部と連携するメリット
1. 最新情報に基づく判断ができる
法改正や通達の動きに迅速に対応でき、判断の迷いを減らせます。
2. 社内リソース不足を補える
特に人事担当者が少人数の企業では、設計から運用までの負荷を軽減できます。
3. 第三者視点でのアドバイスが受けられる
「本当にこの制度で従業員が納得するのか?」という客観的視点が制度の質を高めます。
4. トラブル予防・是正にも効果的
制度導入だけでなく、過去の事例や判例に基づいた実務上のリスク回避策を教えてもらえるのも魅力です。
部分的な相談から始めることも可能
「外部に頼むとコストがかかりそう」「うちのような規模では大げさすぎるのでは?」という声もよく聞かれます。しかし近年では、スポット相談・初回無料・テンプレート提供型など、導入しやすいサービス形態も増えています。
まずは「チェックリストで制度を診断してもらう」「規程のたたき台を作ってもらう」など、部分的な相談から始めることも可能です。無理なく一歩ずつ外部と連携することが、社内制度の質を高める大きな一歩になります。
次章では、この記事のまとめとして、今すぐ始められる休暇制度見直しのステップと、情報収集のポイントをご紹介します。ぜひご活用ください。
休暇制度の見直し、まず何から始める?
実践のためのステップと次のアクション
ここまで、休暇制度に関する社内規程のチェックポイント、運用時のトラブルとその対応、さらに外部リソースの活用法についてご紹介してきました。
しかし、実際に制度の見直しを進めようと思っても、「どこから手をつければいいのか分からない」「人手が足りず進まない」といった声も多く聞かれます。そこで最後に、休暇制度の見直しを実践に移すためのステップをご提案します。
実践ステップ①:現状の規程と運用を「見える化」する
最初に着手したいのは、現在の休暇制度の運用実態を整理し、就業規則や社内規程と照らし合わせることです。
・どんな休暇制度があるか
・その取得状況はどうか
・誰がどのように管理しているか
を「見える化」することで、見直しの優先順位が明確になります。
この段階では、第1章で紹介した「チェックリスト10項目」を使って現状を洗い出すのが効果的です。
実践ステップ②:管理ツールを整備し、属人化を防ぐ
運用改善に取り組む際は、まずExcelなどの管理テンプレートから始めるのも有効ですが、属人化を防ぎ、業務効率化を図るためには、勤怠管理システムの導入も視野に入れるべきタイミングです。
特に休暇の種類が多い企業や、申請承認フローを効率化したい企業では、システムによる一元管理が効果を発揮します。
実践ステップ③:制度を「伝える・使ってもらう」工夫を
制度は整えて終わりではなく、「従業員が理解し、使える状態」にすることがゴールです。運用ルールや申請手順をわかりやすく伝えるマニュアルを用意したり、管理職への制度説明を行ったりといった社内周知が欠かせません。
システムを導入することで、従業員自身が自分の休暇残日数や取得履歴を可視化できるようになり、自発的な制度活用にもつながります。
まとめ:制度と運用を「見直す・整える・伝える」の3ステップで
休暇制度は、従業員の働きやすさと企業の法令順守、そして組織全体の生産性に直結する重要な人事制度です。本記事でご紹介したステップを参考に、ぜひ「見直す → 整える → 伝える」の流れで着実に取り組んでみてください。
フォスターリンクが提供する『HR-Platform人材管理』は、人事情報を一元化し、自在に活用できるクラウドシステムです。
支援実績は20年以上。人事戦略の構築からシステムの導入支援まで一括で行っているため、御社の人事戦略を具体的に仕組み化し、運用までサポートすることが可能です。
KING OF TIMEで、休暇制度運用の課題をまるごと解決
休暇制度の適正な運用を支えるシステムとして、多くの企業で導入されているのが「KING OF TIME 勤怠管理」です。
• 有給休暇、育児・介護休業、特別休暇などの取得状況を自動集計
• 法改正対応にも柔軟にアップデート
• 申請〜承認〜記録まで一気通貫で管理
• 給与計算・人事システムとの連携も可能
人的ミスや担当者の属人化リスクを防ぎ、確実で効率的な休暇管理を実現できます。
システム導入をしたいけれど、何から手を付けてよいかわからない、人手が足りないなどの不安や課題を抱えている企業も多いと思います。
フォスターリンクの提供する『KING OF TIME勤怠 設定代行・運用支援』サービスでは、現状の整理から、システム導入代行まで承ります。上手に活用して進めていきましょう。
\ KOT公認パートナーのフォスターリンクが設定代行から運用支援まで /