年度更新は、企業が労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を正確に計算し、申告・納付するための重要な手続きです。本記事では、人事労務担当者向けに、年度更新の基本的な手順、間違いやすい点、注意点について詳しく解説します。
1. 労働保険料とは
労働保険とは、従業員を1人でも雇用している事業者が加入しなければならない制度で、労災保険と雇用保険の2種類の保険を総称したものです。労災保険は労働基準監督署、雇用保険は公共職業安定所が管轄していて、それぞれに加入手続きが必要となります。
【参考】労働保険の成立手続
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm
2. 労災保険料と雇用保険料
2.1 労災保険料
労災保険料とは、雇用主が従業員のために負担する保険料です。労災保険は、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するための給付等を行っています。
2.2 雇用保険料
雇用保険料とは、雇用主と従業員の双方で負担する保険料です。雇用保険は、労働者が失業した場合の生活支援や再就職活動の支援、職業に関する教育訓練を受けた場合、育児休業や介護休業中の生活支援などのために給付を行っています。
3. 労働保険の対象者
3.1 労災保険の対象者
労災保険は、企業に雇用されて働くすべての労働者が加入する保険です。企業は、パートやアルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働に対償として賃金を受けるすべての労働者を、労災保険に加入させなければなりません。
ただし、労働者を雇用するたびに個別の手続きをする必要はありません。
3.2 雇用保険の対象者
雇用保険の加入対象者は、雇用されて働いている従業員のうち、以下のすべてを満たす人です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上継続して雇用される見込みがある
- 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの
- 4か月以内の期間を定めて雇用される者
- 1週間の所定労働時間が30時間未満である者
- 昼間部の学生ではない(休学中など一部例外あり)
「31日以上継続して雇用される見込み」には、下記のようなケースが該当します。
- 期間を定めずに雇用されている
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない
- 雇用契約には更新規定がないが、過去に同様の雇用契約を締結して31日以上雇用された従業員がいる
雇用保険の要件に該当する従業員を新規に雇用した場合は、雇用した日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する必要があります。
31日が経過してから加入するのではなく、31日以上継続して雇用する見込みがあるか否かで判定する点に注意しましょう。
4. 年度更新の概要
4.1 年度更新とは
年度更新とは、毎年1回、企業が労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を計算し、申告・納付する手続きです。通常、年度更新の対象期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間です。この期間に支払った賃金総額に基づいて、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を算出し、申告・納付を行います。
4.2 年度更新の重要性
年度更新は、企業が法令を遵守し、従業員の福利厚生を確保するために欠かせない手続きです。正確な計算と適時の納付が求められます。手続きの遅延や誤りがあると、延滞金や追徴金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
5. 労災保険料の計算方法と注意点
5.1 労災保険料の計算
労災保険料は、従業員の賃金総額に対して、業種ごとに定められた労災保険料率を掛けて算出します。労災保険料率は、業種の危険度に応じて異なり、危険度の高い業種ほど高く設定されています。
例えば令和7年度の保険料率は、小売業では3/1,000、建設業では18/1,000などとなっています。
※会社の業種が変更となった場合には、事前に変更手続きが必要となりますので、ご注意ください。
5.2 労災保険料計算の注意点
対象労働者の正確な把握
労災保険は、パートタイマーやアルバイトを含むすべての労働者が対象となります。そのため、雇用形態に関わらず、全ての労働者を正確に把握し、賃金台帳や出勤簿などの記録を適切に管理することが重要です。
※代表権・業務執行権を有する役員は、労災保険(労働者)の対象となりません。
賃金総額の正確な集計
労災保険料は、全労働者の賃金総額に基づいて計算されます。そのため、賃金の集計に漏れがないよう、給与明細や帳簿を確認し、正確な賃金総額を算出する必要があります。
年度更新時の適切な申告
年度更新の際には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告します。この際、労働者の賃金総額や保険料率を正確に反映させることが求められます。
申告内容に誤りがあると、後々数年単位で修正対応が発生や給付への影響の可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
労働保険番号の管理
労働保険番号は、労災保険や雇用保険の手続きにおいて必要となる重要な情報です。労働保険番号を適切に管理し、必要な手続きの際に正確に使用することが求められます。
(番号が不明の場合には、年度更新の紙申告書に記載があるので、確認してみましょう)
6. 雇用保険料の計算方法と注意点
6.1 雇用保険料の計算
雇用保険料も、従業員の賃金総額に対して、業種ごとに定められた雇用保険料率を掛けて算出します。雇用保険料率は、一般の事業、農林水産業、建設業などの業種によって異なります。
また、雇用保険料は事業主と労働者の双方が負担するため、計算時にはそれぞれの負担割合を確認する必要があります。
6.2 雇用保険料計算の注意点
以下の点に注意して、都度の正確な事務処理を心がけ、年度更新作業を実施しましょう。
被保険者資格の取得手続き
新たに労働者を雇用した場合、雇用保険の加入条件を満たす労働者については、「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用した日の属する月の翌月10日までに所轄のハローワークに提出する必要があります。
離職時の手続き
労働者が退職した場合には、「雇用保険被保険者資格喪失届」や「離職票」の作成・提出が必要です。特に離職票は、労働者が失業給付を受ける際に必要となるため、速やかに手続きを行いましょう。
賃金総額の正確な集計
雇用保険料は、雇用保険の被保険者に支払われた賃金総額に基づいて算出されます。
保険料率の確認と適用
雇用保険料率は、業種や年度によって異なる場合があります。最新の料率を確認し、正確に適用することが重要です。特に年度更新の際には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を正確に計算し、申告・納付を行う必要があります。
高年齢被保険者の取り扱い
現在は65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用対象となります。
【参考】雇用保険の適用拡大等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/tekiyokakudai.pdf
7. 年度更新の手続き
7.1 賃金総額の集計
前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の賃金総額を集計します。労働保険の対象賃金範囲を事前に確認しておきましょう。。
【参考】労働保険対象賃金の範囲
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-07.pdf
7.2 保険料率の確認
労災保険料率と雇用保険料率を確認します。これらの料率は毎年変更される可能性があるため、最新の情報を厚生労働省や労働局のウェブサイトで確認することが必要です。
【参考】令和7年度保険料率
- 労災保険料率
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html - 雇用保険料率
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
7.3 保険料の計算
集計した賃金総額に保険料率を掛けて、労災保険料と雇用保険料を計算します。計算ミスを防ぐために、複数回確認することをおすすめします。また、計算支援ツールを活用することで、正確かつ効率的に計算が可能です。
7.4 申告書の作成
労働保険年度更新申告書を作成します。申告書には、賃金総額や計算した保険料の詳細を記載します。申告書の様式や記入方法は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
【参考】令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html
7.5 申告・納付
労働保険年度更新申告書を、管轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または金融機関に提出し、保険料を納付します。納付方法には、窓口持参、郵送、電子申請などがあります。納付期限を守ることが重要で、期限を過ぎると延滞金が発生する可能性があります。
労務担当者は労働保険に関する手続きを正確かつ迅速に行うことが求められます。不明点がある場合は、毎年届く年度更新用の封筒にコールセンターの案内が入っておりますのでご確認ください。
また詳細な部分で確認事項が発生した場合には、管轄のの労働基準監督署や顧問の社会保険労務士の先生に申告前に相談しましょう。
給与計算をアウトソーシングすることで、改めて各手当の内容や意味を確認・理解し、対象賃金範囲の整理が可能です。また、給与情報を自社とは別に管理保管しておくことができるメリットがあります。
フォスターリンクのHR-Platform 給与計算では、月々の給与計算からWeb給与明細作成までお任せいただけます。勤怠や年末調整のシステム化や社会保険届出業務などもオプションにて幅広く対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
\ フォスターリンクの給与計算代行サービスを詳しく解説 ダウンロードはこちらから /

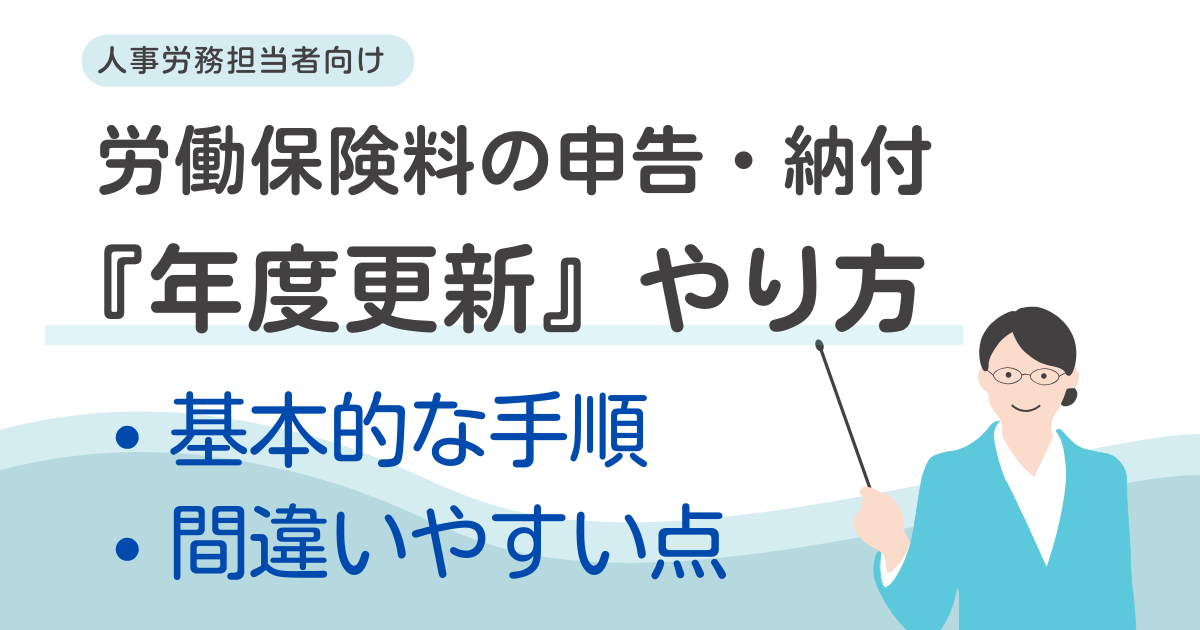


.jpg?width=624&height=427&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%20(2).jpg)
