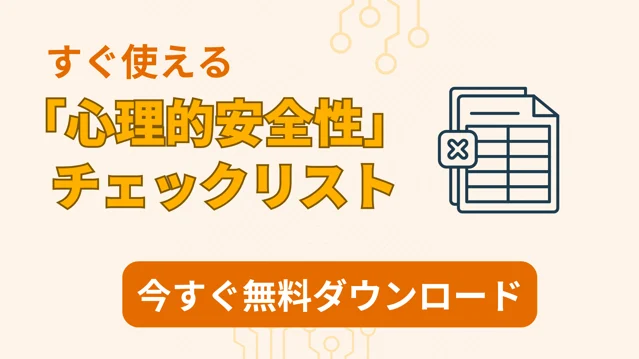近年、企業の持続的成長に欠かせないキーワードとして注目されているのが「心理的安全性」です。
本稿では、「心理的安全性」の本当の意味とその必要性、さらに心理的安全性を高めるための組織づくりのポイントをお伝えします。
▼今すぐチェックリストをお試しいただく方はこちらかダウンロード
1. なぜ今「心理的安全性」なのか?
「心理的安全性」とは、端的に表現すると、チームメンバーが罰や否定を恐れずに、率直に意見を述べたり、質問・提案・失敗を共有できる状態を指します。単なる「仲良し」ではなく、健全な対話と挑戦が許容される職場環境のことです。
この概念が広く知られるようになったきっかけは、Googleが2012年から実施した「プロジェクト・アリストテレス」の研究です。社内の180以上のチームを分析した結果、チームの成功要因として最も重要だったのが「心理的安全性」であることが判明しました
特に日本企業においては、年功序列や上下関係が強く残る文化の中で、若手社員や中途採用者が意見を言いづらいという課題が根強く存在します。こうした背景もあり、心理的安全性の確保は企業経営の重要なテーマとなっています。
経営者や人事担当者にとって、心理的安全性は単なる「雰囲気づくり」ではなく、組織の成果に直結する経営課題と言えます。
次の章では「心理的安全性」についてもう少し詳しく紐解きながら、経営課題と言える理由を確認してきましょう
2.心理的安全性とは?
「心理的安全性」という言葉は、近年ビジネス界で広く使われるようになりましたが、その意味を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。まずは定義を明確にし、よくある誤解を整理しておきましょう。
2-1.Google「プロジェクト・アリストテレス」から学ぶ心理的安全性の本質
心理的安全性という概念が世界的に注目されるようになったきっかけの一つが、Googleが2012年から実施した社内研究「プロジェクト・アリストテレス(Project Aristotle)」です。このプロジェクトは、「成功するチームにはどんな共通点があるのか?」という問いに答えるために始まりました。
背景と目的
Googleは、世界トップクラスの技術者や研究者を抱える企業でありながら、すべてのチームが同じように成果を出しているわけではないことに着目しました。
そこで、180以上のチームを対象に、構成・スキル・性格・働き方・コミュニケーションスタイルなど、数百項目に及ぶデータを収集・分析し、チームの生産性や創造性に影響を与える要因を探ったのです。
分析と発見
当初、Googleの研究者たちは「優秀な人材が集まっているチームほど成果が高い」「似た性格や価値観を持つメンバーが集まるとうまくいく」といった仮説を立てていました。しかし、データ分析の結果、個々の能力や性格よりも、チーム内の“雰囲気”や“関係性”が成果に強く影響することが明らかになりました。
そして最終的に、成果を出すチームに共通していた、以下5つの要素にたどり着きました。
その中でも最も重要な要素が「心理的安全性」だったのです。
チームの
| 心理的安全性 | 「無知、 |
| 相互信頼 | 相互信頼の低いチームはお互いに責任転嫁をしあう |
| 構造と明確さ | 職務上で |
| 仕事の意味 | 仕事そのもの、またはその成果に対して目的意識を感じられる |
| インパクト | 自分の仕事には意義があるとメンバーが主観的に思える |
引用:Google re:Work
心理的安全性の定義
Googleは心理的安全性を次のように定義しています
『「無知、
つまり、チームメンバーが、自分の考えや疑問、懸念、失敗を率直に共有しても、恥をかいたり罰されたりすることなく受け入れられると感じられる状態があることで、メンバーは安心して発言でき、アイデアの提案・問題の指摘・質問・助けの要請などが活発に行われるようになります。
成果への影響
心理的安全性が高いチームでは、以下のような成果が観察されました
- ミスの報告が増える(=改善が進む)
- アイデアの質と量が向上する
- メンバー間の信頼が深まり、協働が促進される
- 離職率が低下し、定着率が向上する
特に注目すべきは、「ミスの報告が多いチームほど成果が高い」という逆説的な結果です。これは、ミスが多いのではなく、安心して報告できる環境があるからこそ、早期に対処でき、学習が進むということを意味しています。
実務への示唆
この研究は、単なる学術的な知見にとどまらず、マネジメントや組織開発の実務に大きな影響を与えました。Googleではこの結果を受けて、以下のような取り組みを進めています
- マネージャー向けに「心理的安全性を高めるリーダーシップ研修」を実施
- チーム内でのフィードバック文化の醸成
- 1on1ミーティングや対話の場の制度化
- チームの状態を可視化するサーベイの導入
このように、「プロジェクト・アリストテレス」は、心理的安全性が単なる“良い雰囲気”ではなく、組織の成果に直結する科学的・実証的な要素であることを示した画期的な研究です。日本企業においても、これを参考にした制度設計やマネジメント改革が進みつつあります。
2-2.よくある誤解
「心理的安全性」の意味について、よく聞かれる誤った解釈をご紹介します
誤解①:「仲良しグループ」や「同調に満ちた”ぬるい”職場」のこと?
心理的安全性は、単なる「仲が良い」状態ではありません。むしろ、率直なフィードバックや建設的な対立が許容される環境が「心理的安全性の高い職場」であり、重要なのはそこで率直なフィードバックや建設的な意見の対立が発生することです。そういったことが発生しない、雰囲気の優しい、仲良しの、緩い職場、といった意味ではありません。
誤解②:「甘やかし」や「厳しさの排除」?
心理的安全性は、厳しさや高い基準を否定するものではありません。むしろ、高い目標に向かって挑戦するための土台です。安心して失敗できるからこそ、挑戦が生まれ、学習が促進されるのです。
誤解③:「心理的安全性=メンタルヘルス」?
もちろん関連性はありますが、心理的安全性は組織文化やチームの関係性に関する概念であり、個人のメンタルヘルスとは異なります。メンタル不調の予防にもつながりますが、目的やアプローチは別物です。
3.従業員からみた心理的安全性の必要性
リクルートマネジメントソリューションズによる調査レポート「チームリーダー516人に聞く、心理的安全性の必要性や効能」によると、管理職やリーダー自身も、心理的安全性の必要性やその効果を重要視していることが見て取れます
調査概要
対象:従業員規模100名以上の企業で、3名以上のメンバーを率いる正社員(管理職・一般社員含む)
有効回答数:516名
調査目的:心理的安全性の認知度、必要性、職務特性との関係、チーム成果や心身疲労との関連を明らかにすること
3-1.主な調査結果
② 「心理的安全性」の必要性の認識
「必要」「やや必要」と答えた人が全体の7割以上

引用:リクルートマネジメントソリューションズによる調査レポート「チームリーダー516人に聞く、心理的安全性の必要性や効能」
必要とされる理由:
- 情報共有の促進
- 多様な意見による創造性の向上
- リスクの早期発見
- ストレス軽減、モチベーション向上
③「心理的安全性」と「チーム成果」との関係
成果が高いチームほど、以下の特徴が顕著:
- 問題点や困難な論点を提起できる
- 他者の反応に配慮したコミュニケーションがある
- メンバーが互いの技術や才能が評価され活用されると感じている
④「心理的安全性」と「心身疲労」との関係
疲弊度が高いチームほど、以下の特徴がある:
- 失敗した人がいたらその人が悪く思われることが多いと感じている
- 異質な人を拒絶するメンバーがいると感じている
- チームメンバーに助けを求めることがむつかしいと感じている

引用:リクルートマネジメントソリューションズによる調査レポート「チームリーダー516人に聞く、心理的安全性の必要性や効能」
3-2 調査結果が示唆するもの
この調査は、心理的安全性が、組織マネジメントをする上で、チームの成果に直結するだけでなく、メンバーの心身にも影響を与える重要な要素であることを示しています。
4.心理的安全性を高めるための施策
心理的安全性を高める組織開発のステップとして、以下の5つが重要になります
- チームの実態を”見える化”する
- チームの目的を”共有”する
- ルールを作る
- 場を作る
- 人の関係性を作る
(引用:青島未佳(2021)『心理的安全性ガイドブック』労政時報)
これらは、単なる「雰囲気づくり」ではなく、制度設計やマネジメントの仕組みとして組み込むべき要素です。
4-1.チームの実態を”見える化”する
目的:心理的安全性の現状を把握し、課題を明確にする。
施策例:
- 組織サーベイを活用し、チームごとの心理的安全性スコアを可視化。
- 社員アンケートで「発言しやすさ」「ミス報告のしやすさ」「上司との信頼度」などを定量的に測定。
- 360度評価で、個人のコミュニケーションスタイルや、相互の信頼関係を多面的に把握。
4-2.チームの目的を”共有”する
目的:チームをマネジメントする真の目的である「業務上の目的」を明確にし、メンバーが共有する。
「心理的安全性」を作ることが本来の目的ではない。本来の目的の共有がなければ、結果的に"優しい職場""居心地の良い職場"をつくってしまいかねない。」
(引用:Web労政時報 “心理的安全性が高い”チームの新たな視点 - 第5回・完 心理的安全性のつくり方 2022)
施策例:
- 経営層が「会社のミッション・ビジョン・バリュー」と現場の業務をつなげるメッセージを発信
- 目的が不明瞭な業務については、上司が背景や期待を丁寧に説明する場を設ける
- プロジェクト開始時に「目的・背景・期待される成果」を明確に共有
- 人事評価制度に「目的への貢献度」や「目的に沿った行動」を評価項目として組み込む
- チーム内で「私たちの仕事の目的は何か?」を話し合うワークショップを実施
4-3.ルールづくりと実行
目的:安心して発言・行動できるための行動指針やルールを整備する。
施策例:
- 「否定しない」「遮らない」「感謝を伝える」など、ミーティング時の行動ルールを明文化。
- 1on1ミーティングのガイドラインを作成し、上司・部下双方が安心して話せる枠組みを提供。
- チーム内で「フィードバックは事実ベースで、人格否定はしない」などの原則を共有。
- 経営層や管理職から積極的に実行し、形骸化させない。
4-4. 対話の場づくり
目的:率直な意見交換ができる場を定期的に設ける。
施策例:
- 月1回の「心理的安全性チェックイン」ミーティングを実施し、最近の不安や気づきを共有。
- テーマを決め、社内ファシリテーターによる対話型ワークショップを実施。
- コミュニケーションツールなどを活用し、目安箱のような匿名でフィードバックできる仕組みで言いづらい声を拾う。
4-5. 人の関係性を作る
目的:信頼関係を醸成するベースを作る。
施策例:
- メンバー間での1on1。
- ランチ会やサークル活動
- 「会議前のアイスブレークタイム」(雑談を交わす時間)
- 同僚の貢献を認め合う制度
5.【無料DL】心理的安全性チェックリストのご紹介
フォスターリンクでは、以下のようなフォーマットの心理的安全性チェックリストを無料でご提供しています。
☑️誰でもすぐに使えるシンプルフォーマット
☑️どんな組織でも適応できる汎用的な項目
☑️5つのカテゴリ/全15問で網羅的に、かつ負担なく回答できる
▼支援実績20年以上!弊社の心理的安全性チェックリストを確認したい方は、こちらからダウンロードください。
6.まとめ |心理的安全性は意図的に設計・運用
心理的安全性は、自然に育つものではなく、意図的に設計・運用すべき組織課題です。阻害要因を放置すれば、組織やチームの成果に影響するだけでなく、離職率の上昇やイノベーションの停滞にもつながります。まずは現状を見える化し、対話と制度の両面から改善を進めることが、強い組織づくりの第一歩です。
フォスターリンクでは、心理的安全性を高めるための制度設計のご支援から、サーベイや人事評価制度運用のためのツール、アウトソーシングまで幅広いソリューションをご用意しています。
何から取り掛かればよいのかわからない、という場合には、そこを整理するところから丁寧にご支援いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
7.参考文献
Google re:Work
青島未佳(2021)『心理的安全性ガイドブック』労政時報
Web労政時報 “心理的安全性が高い”チームの新たな視点 - 第5回・完 心理的安全性のつくり方 2022

.png)