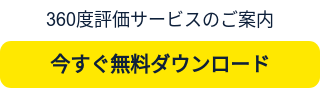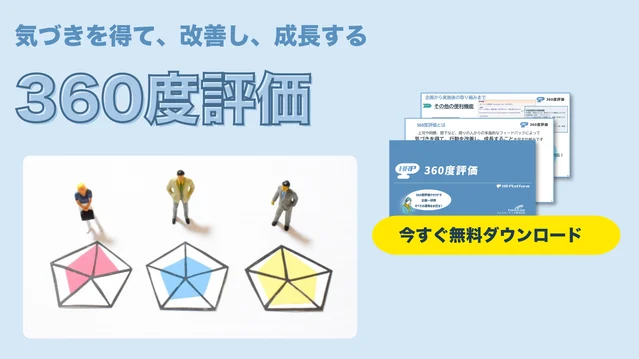360度評価は、上司、同僚、部下、そして自己評価を組み合わせて行う多面的な評価方法です。個人の強みや改善点に対する「気づき」がその人の成長を促すため、多くの企業で採用されています。
しかし、適切に運用をしないと、逆に社員の士気を下げてしまう危険性があります。
今回は多面評価実施の落とし穴と、社員の士気を下げない5つの運用ポイントをご紹介します。
多面評価制度の落とし穴とは
一人の上司が評価する場合も、上司・同僚などの複数人が評価する場合も、人が人を評価することですので、完璧な運用というのは難しいものです。360度評価ならではの落とし穴は、主に以下のようなことが挙げられます。
1)匿名性の欠如がもたらす影響
評価者の匿名性が担保されない場合、正直なフィードバックが得られにくくなります。評価者が報復を恐れて、本意と違う評価をしてしまう可能性があります。
2)評価方法の偏りや不正な評価
- ハロー効果
ハロー効果とは被評価者の著しい1つの特徴に対する評価により、他の部分への評価が影響をうけてしまいがちになる状態を言います。例えば、「〇〇さんはいつも営業成績が良い。今回営業成績が低迷しているが、たまたまだろう」とか、逆に「普段から遅刻や忘れ物が多い。今回の営業成績が良いのはたまたまだろう」というようなものです。
評価をする際に自分のイメージに加え、周囲が持っているイメージにも引っ張られてしまう状態を指します。
- 談合
上司や部下、また互いに評価対象になる周囲の同僚に甘い評価をつけることで、自身に高い評価の見返りを求めるというケースも、往々にして発生しやすいといえます。職場内で同じようなことを考えるメンバーが増えてくると、このような評価時に事前の談合が生まれるリスクも考えられます。
- 好き嫌いによる評価
多面評価では、複数の部下が同じ一人の上司に対して評価を実施することになります。そのため、本来の上司としての能力の良し悪しではなく、性格面や相性が合わない上司に対し、部下同士で事前に口裏を合わせて嫌いな上司の評価を著しく低くつける、というリスクもあります。
- 過度な批判
たとえ匿名性を確保しても、過度な批判が集まりすぎると、被評価者のモチベーションを大きく損ないます。
3)評価基準の曖昧さ
評価基準が明確でなかったり、評価者全員が理解していないと、評価が主観的になり、公平性を欠く恐れがあります。
4)フィードバックが適切でない、フィードバックがない
評価を行っても、フィードバックがない、あるいは不十分である場合、被評価者が自己改善のための具体的な行動を起こすことが難しくなります。結果として被評価者の成長の機会を逃してしまいます。
また、フィードバックの質だけでなく、タイミングも重要です。被評価者がその評価に対して抱く感情が冷めてしまい、改善への意欲が薄れてしまいます。
5)時間やリソース、心の負担が重い
評価の実施やフィードバックの提供には時間とリソースがかかります。それが過度になると、日常業務に支障をきたすことがあります。
また、「周囲が常に自分を見ている・評価されている」と、自身の一挙手一投足を常に観察されているという疑心暗鬼になりやすく、結果職場の雰囲気を壊してしまう可能性があります。
正しい評価をしようという目的で多面評価を導入しても、このような社員の士気低下につながってしまっては本末転倒です。
全体の士気を下げないための運用法
上記のような士気低下を防ぐため、多面評価導入時には以下の運用方法をセットでご検討ください。
なお、360度評価の運用ポイントについては、こちらの記事でも紹介しています。
【関連記事】360度評価 うまく運用できるポイント4項目を解説
1)匿名性担保のためのツール利用
外部の評価ツールやプラットフォームを利用することで、評価者の匿名性を確保できます。例えばクラウドシステム「HR-Platform 360度評価」では、評価者の匿名性を担保し、複数の評価結果をまとめて報告することが可能です。
2)事前説明会の実施
多くの会社において、この事前説明がなされないまま、「今期から多面評価を取り入れる」と一方的にアナウンスされるケースが見受けられます。意図が現場に伝わらない制度は、社員にとっては業務負荷と捉えられてしまう恐れがあります。
多面評価を導入する狙いや明確な評価基準・方法に関して、説明会を実施し、通達を行うことで、対象となる社員全てに十分理解をしてもらうことが必要です。
なお、360度評価の実施手順については、こちらの記事でも紹介しています。
【関連記事】経営者必見!『360度評価』の実施手順
3)能力開発のために評価結果を用いることを明らかにする
また、この多面評価を社員の能力開発に用いる場合、「昇進・昇格・昇給などの査定には使わない」と説明した方が良いでしょう。
あるメーカーでは、報酬に反映しない前提で多面評価を実施したところ、「複数の人に評価されることで公平さを感じられる」という声が聞かれています。適正に運用することで、人材育成の指標づくりに役立つでしょう。
4)定期的なフィードバックセッションを設ける
評価後にフィードバックセッションを設け、被評価者がフィードバックを理解し、具体的な改善策を立てられるように支援します。フィードバックは一度きりではなく、定期的に行うことが重要です。
例えば、四半期ごとにフィードバックセッションを設け、評価者と被評価者が継続的にコミュニケーションを取ることで、評価結果を基にした継続的な改善が可能となります。
360度評価の正しい運用が、社員の成長につながる
多面評価は、自己評価だけでなく、上司、同僚、部下からのフィードバックを通じて、自分の強みや改善点を客観的に知ることができる貴重な機会です。しかし、適切な運用ができないと、不正や士気低下を引き起こすリスクが潜んでいます。
多面評価を導入する際は、企画からシステムも含めた全体運用を任せられる外部企業と協力することによって、それらのリスクを排除し、社員の成長につなげることができます。